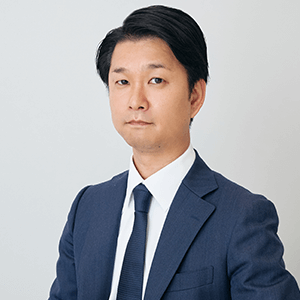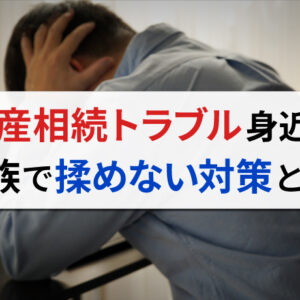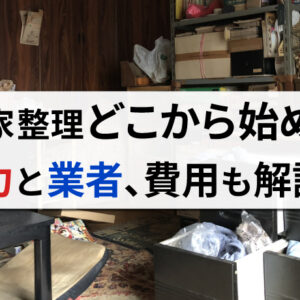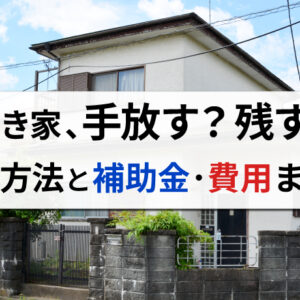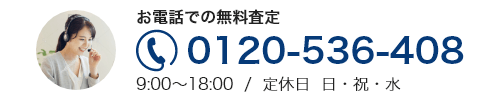について今すぐご相談できます。
お電話する
道路にはいくつかの種類があり、その種類によって土地の活用が制限されることがあります。多くの人にとって「私道」と「公道」の意味をなんとなく理解はしていても、どの道路が私道なのか把握している方は少ないと思われます。
同様に私道の場合、再建築ができない可能性があることを知っている方も多くはないでしょう。
そこで今回は、再建築不可になる私道について紹介します。また、不動産の前の道路が私道だった場合の対処法もあわせて解説しますので、ぜひお役立てください。
目次
公道と私道の違い
まずは、公道と私道のちがいについて説明します。
公道とは
公道は、国または自治体が所有し管理する道路のことを指します。これらの道路は公共の利益のために整備され、誰でも利用することができます。
しかし、公道を利用する際には道路交通法が適用されるため、車両を運転する場合には運転免許証が必要です。
私道とは
一方、私道は個人や団体が所有する道路で、国や自治体による管理はされていません。私道では運転免許がなくても車両の運転が可能であり、自動車教習所の敷地などが一例です。
ただし、私道の通行に関する許可は所有者によって管理され、通行を制限することができます。よく「関係者以外通行禁止」といった立札を見かけるのは、そのためです。
私道の所有者とは、下記のとおり。
【私道の所有者】
- 地主
- 土地を購入した人たちの共有名義
- 土地を購入した人たちで私道を分筆して持つ
私道負担とは
不動産取引において「私道負担」という言葉を目にすることがあります。これは、不動産が私道に接している場合に、その私道の維持や管理に関わる責任を意味します。
特に、法律上「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」という接道義務があり、私道を設けることでこの義務を満たすことがあります。これをセットバックと呼び、この場合も「私道負担」とされます。
私道には固定資産税がかかる
私道の所有者は、その土地に関する固定資産税の支払い義務を持ちます。単一の地主が全ての私道を所有している場合や、セットバックにより自己の敷地を私道にした場合は、その所有者が税金を全額負担します。複数人で私道を共有している場合や分筆した場合は、各々がその持分割合に応じた税金を支扲うことになります。
ただし、私道が自治体によって位置指定道路として認められ、特定の要件を満たしている場合、固定資産税が課されないこともあります。この点は自治体によって異なるため、詳細は各自治体へのお問い合わせが必要です。
関連記事:共有持分になっている私道とは?トラブル事例や売却時の注意点を紹介
公道か私道か調べる方法
公道と私道を区別する方法は一見すると明確ではありませんが、いくつかの方法で確認することができます。「私道」という立札が目印の1つですが、他にも確実な方法がありますので、以下より解説します。
役所で確認する
地域の役所、具体的には道路管理課や建築指導課などの窓口で、その道路が公道か私道かを確認することが可能です。また、自治体によってはオンラインで情報を確認できることもあります。
公図で確認する
法務局で入手できる公図を使用する方法もあります。公図とは土地の形状や地番が記載された地図で、公道は通常地番が割り当てられていないため、地番がある道路は「私道」と判断できます。地番は、不動産登記情報を管理するための一筆ごとに定められた番号です。
公道でも私道でも、法律上の「道路」であれば再建築できる
公道と私道の違いを把握した上で、重要なのは法律上「道路」と認められているかどうかです。これにより再建築が可能かどうかが決まります。
法律上の道路の定義
建築基準法で定められている道路の定義とは、下記の通りです。
<建築基準法で定められている「道路」>
- 法42条1項1号道路:道路法に基づく国道、都道、区道などの公道。
- 法42条1項2号道路:都市計画法や土地区画整理法などに基づき認可を受けてつくられた開発道路。
- 法42条1項3号道路:1950年以前または都市計画区域指定時以前に存在し、幅員4m以上の既存道路。
- 法42条1項4号道路:新設または変更予定の計画道路。
- 法42条1項5号道路:私人が築造し、特定行政庁が位置を指定した私道。
- 法42条2項道路:1950年以前または都市計画区域指定時以前に存在し、幅員4m未満で一定条件を満たす道。
- 法43条1項ただし書適用道路:42条に該当しないが、過去に43条1項ただし書の適用を受けた道。
これらの定義に該当する道路であれば、公道であっても私道であっても、再建築が可能です。特に私道の場合、「位置指定道路」として認められると再建築に大きな影響を与えます。
位置指定道路と認められるための要件
私道が位置指定道路として認められるためには、いくつかの条件があるのでご紹介します。
- ①:道路幅が4m以上
- ②:両端が他の道路に接続していること
- ③:接道する道路と交わる部分に隅切りがある
- ④:ぬかるみ防止をしていること
- ⑤:縦断勾配が12%以下
- ⑥:排水設備を設けること
②の道の両端が他の道路につながっている必要があります。ただし、道が行き止まりになっている袋路状道路の場合でも、要件を満たせば認可が可能です。袋路状道路の要件ついてはのちほどお伝えします。
③の隅切りとは、角地の土地の角を道路状にすることです。公道への接道部分に両端2m以上の隅切りが必要です。見通しを良くしたり車両の転回に要する幅を確保したりすることが目的です。
通り抜けができない袋路状道路でも、以下を満たせば位置指定道路として認められることがあります。その場合の条件については、以下のとおりです。
【袋路状道路の場合の条件】
- 道路延長が35m以下である
- 道路延長が35mを超える場合は転回スペースがあること
- 幅員6m以上であること
- 接道する道路と交わる部分に隅切りがある
位置指定道路の認可を受ける流れ
私道を位置指定道路として認めてもらうプロセスは以下の通りです。地域によって手続きの詳細は異なるため、最終的には各自治体に確認が必要です。
- 手順①:事前相談
- 手順②:申請書の提出
- 手順③:審査
- 手順④:工事着手
- 手順⑤:工事完了検査
まずは役所へ行ってすれば、申請書の説明や必要書類を教示してくれるでしょう。指定申請書や必要な書類を役所へ提出し、本申請を行います。
審査後、問題がなければ「受理通知書」が交付され、道路の工事に入ります。工事着手は申請書受付前でも可能な場合があります。
工事が完了したあとに検査を行い、問題がなければ位置指定道路として認められます。
位置指定道路にも関わらず再建築不可になるケース
上記の条件をクリアし、関係権利者の承諾をもとに申請手続きをしている道路が位置指定道路として認められます。
しかし、位置指定道路として認められているにも関わらず、再建築できないケースがありますので、以下よりみていきましょう。
幅員が4m以下の不完全な位置指定道路
位置指定道路として認められるためには通常幅員が4m以上必要ですが、歴史的な市街地等に存在する幅員4m未満の道路もあります。これらの道路は位置指定道路として認められていても、建築基準法に基づく再建築の基準を満たさない場合があります。
昔と今で道路位置が異なる場合
長い間存在している位置指定道路の場合、過去に提出された図面と現在の道路の位置が異なることがあります。このような状況では、再建築の際に問題が発生する可能性があります。
再建築前に確認すること
再建築する前に確認すべきことを紹介します。具体的には、以下のとおり。
- 法律上の「道路」である位置指定道路か確認
- 所有者の同意を得る
それぞれ個別に解説します。
法律上の「道路」である位置指定道路か確認
再建築を計画する前に、その道路が法律上の「道路」として位置指定されているかを確認することが重要です。
これは、役所の建築課などの窓口で図面を閲覧することで確認できます。自治体によっては「指定道路調書証明書」として道路位置指定図の写しを提供していることもあります。
所有者の同意を得る
私道の所有者からの同意は、再建築において必須の要件です。特に、私道が複数の所有者によって共有されている場合、全所有者の同意が必要になることが多々あります。
同意書の作成は、口頭での約束ではなく文書化することが重要。これにより、将来的なトラブルを防げるのです。
【同意書に記載する内容】
- 日付
- 同意内容
- 同意する旨
- 署名
- 捺印
同意書には、私道の所有面積の変更に伴って他の共有者の持分に影響がない旨を明記することが推奨されます。
再建築できない場合の対処法
土地が私道に面しており、位置指定道路としての認定が受けられず再建築が難しい場合、対応策は何があるのでしょうか。解決方法としては、以下のものが考えられます。
- セットバックする
- 建築基準法第42条2項道路として認可を受ける
- 建築基準法第43条ただし書き道路の申請
それぞれ詳しく解説します。
セットバックする
道路の中心線から2m以上土地を後退させる「セットバック」を行うことで、位置指定道路としての認定を受ける可能性があります。道路の中心線を特定するには、役所の建築指導課での確認が有効です。
セットバックによって建築可能な土地は狭くなりますが、その代わりに再建築の承認が得ることが可能。自治体によってはセットバックに関する費用の補助を行っている場合もあります。
建築基準法第42条2項道路として認可を受ける
位置指定道路ではない私道でも、建築基準法第42条2項に基づく「みなし道路」としての認可を受けることで、再建築が可能になるケースも存在します。
これは建築基準法施行前から存在する幅員4m未満の道路に適用され、特定行政庁の指定を受ける必要があります。再建築には私道の所有者全員の同意が必要で、この場合は「私道負担同意書」の作成が求められます。
建築基準法第43条ただし書き道路の申請
私道が位置指定道路や法律上の道路として認められていない場合でも、敷地が広い公園や広場に面しているならば、建築基準法第43条のただし書きに基づく申請を通じて、建築許可が下りる可能性があります。
この規定は、災害時の消防車や救急車のアクセスや避難経路を確保することを目的としています。そのため、幅員4m未満であっても十分なスペースが確保されていれば、特別な条件下で建築許可が認められることがあります。
まとめ
「私道で再建築ができない」「位置指定道路の所有者から同意を得られない」など、再建築ができずにお困りの場合はプロに相談しましょう。私道に接する不動産の建て替えは、権利関係や法律などの問題が関わってきます。独断で対処することによってさらなるトラブルを生む前に、専門家に頼ることでスムーズに対処できます。
再建築の相談から実際に建築できるまで時間を要することがあります。余裕をもって早めに依頼することをおすすめします。
本ブログで情報発信を行っている「ワケガイ」は、訳あり物件を積極的に買い取っている専門業者です。所有物件についてお悩みの方は、訳あり物件の買取に特化したワケガイに、ぜひお問い合わせください。
| 運営団体 株式会社ネクスウィル 2019年1月29日設立。訳あり不動産の買取を行う不動産会社。相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産を買い取り、法的知識や専門知識を以って、再度市場に流通させている。 |