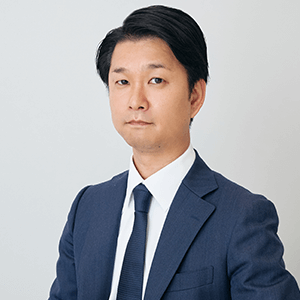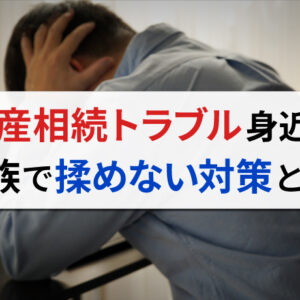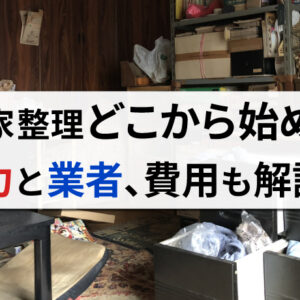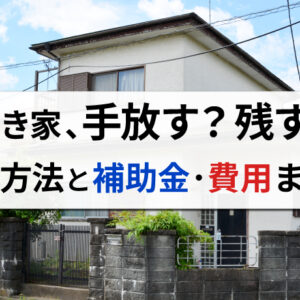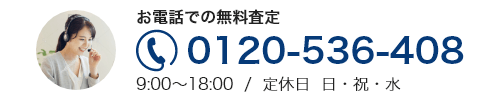について今すぐご相談できます。
お電話する
賃貸マンションやアパートなどを経営していると、入居者とトラブルが発生してしまうケースがあります。入居者との問題が解決せず、「退去してほしい」と考える場合もあるでしょう。
しかし、入居者が「退去したくない」という意思を持っている場合、スムーズな立ち退きが難しくなります。
そこで今回は、入居者に立ち退き交渉をするときの流れや、交渉がうまくいかないときの対処法などを解説します。
賃貸マンションやアパートなどを経営していると、入居者とトラブルが発生してしまうケースがあります。そこで今回は、入居者に立ち退き交渉をするときの流れや、交渉がうまくいかないときの対処法などを解説します。
立ち退きとは
「立ち退き」とは、賃貸物件に住む賃借人が、さまざまな理由でその場所から退去することを指します。通常、物件のオーナー(賃貸人)からの要求によって行われます。
立ち退きを要求できるケース
賃貸人が立ち退きを要求するには正当な理由が必要です。どのような状況が「正当な理由」とみなされるか、いくつかの典型的な例を挙げると以下のケースが考えられます。
- 賃借人が家賃を滞納している場合
- 賃借人が契約違反をしている場合
- 不法占拠されている場合
- 建物の使用を必要とする事情がある場合
- 立建物が老朽化したため建て替える場合
次項より、個別にみていきましょう。
賃借人が家賃を滞納している場合
賃借人が長期間にわたり家賃を滞納している、あるいは滞納が頻繁に発生している場合、賃貸人は立ち退きを要求する権利を持ちます。
一般的に、3ヶ月の滞納が一つの目安とされています。ただし、過去の賃借人との関係や滞納時の対応の仕方によって、立ち退きの可否が決まることもあります。
賃借人が契約違反をしている場合
賃貸借契約で定められたルールを賃借人が破った場合、立ち退き要求が正当化されます。例えば、契約上禁止されている他人の同居やペットの飼育などがこれに該当します。
不法占拠されている場合
法的な根拠なしに物件を占拠している場合は「不法占拠」とされ、賃貸人は立ち退きを要求する権利があります。
建物の使用を必要とする事情がある場合
物件の所有者に特別な事情が生じた際、例えば所有者が仕事の都合で物件に戻る必要がある場合など、賃貸人は立ち退きを要求できます。
ただし、この種の要求は一定の金銭的補償(立ち退き料)を伴うことが多々あります。
立建物が老朽化したため建て替える場合
耐震性などの不備が発生した古い建物の場合、補強や建て替えが必要になることがあります。
このような状況では、立ち退き料の支払いを伴いながら立ち退きを要求することが一般的。しかし、建物の老朽化が極端で重大な危険を伴う場合、立ち退き料なしでの要求も可能です。
関連記事:借地の立ち退き交渉で知っておくべきことを詳しく解説
立ち退きを要求できないケース
不動産の賃貸人が立ち退きを要求する際、正当な理由が必要であり、主観的な不満や「賃借人の性格や人間性が気に入らない」などの理由では、要求は認められません。
賃貸借契約の更新に関しては、地域や契約によって異なりますが、基本的には賃借人側の意志で更新を拒否することは可能です。
しかし、賃貸人側が次回の更新を拒否する場合でも、前述したような正当な理由がなければ、立ち退き要求はできません。
立ち退きの「正当な理由」に明確な定義はない
立ち退き要求に必要な「正当な理由」には明確な定義がなく、賃貸人と賃借人の双方の事情を考慮して判断されるケースもたびたび発生します。信頼関係の破壊など一方的な契約解除の理由として考慮されることもあります。
しかし、似たケースでも裁判により異なる判断が下されかねないため、他の事例を参考にする際は慎重である必要があります。
関連記事:立ち退きしてもらうのに必須の「正当事由」とは?実現に必要な条件を詳しく解説
立ち退き料とは
立ち退き料は、賃貸人の都合で退去を要求された賃借人に対して、引っ越し費用や新居の敷金、礼金、仲介手数料などの費用を補償するために支払われます。
これはあくまで慣習であり、法律上の義務ではないことに注意が必要。立ち退き料を支払うことが、必ずしも退去の正当化につながるわけではありません。
立ち退き料の目安
立ち退き料には確固たる決まりはなく、一般的には「家賃6ヶ月分プラス引っ越し費用」が支払われることが多いですが、必要な費用には個人差があります。
したがって、賃貸人と賃借人間で金額に関する交渉が行われることもあります。
関連記事:立ち退き料の相場はどのくらい?計算方法や料金を抑える方法を解説
立ち退き料が発生しない場合
立ち退き料は主に賃貸人の都合による退去要求の場合に発生します。これには、建物の使用が必要な事情や建物の老朽化による建て替えなどが含まれます。
一方で、賃借人の家賃滞納や契約違反などの理由での退去の場合は、立ち退き料が発生しないことが一般的です。
立ち退き交渉の流れ
「賃借人に立ち退きをお願いしたい」と考えた場合、どのような流れで要求したらいいのでしょうか。立ち退き交渉の流れは、下記のようになります。
- 手順①:立ち退き請求書を送る
- 手順②:話し合いは文書や録音で残しておく
- 手順③:退去手続きをする
それぞれ、個別に解説します。
手順①:立ち退き請求書を送る
立ち退き要求をする際には、まず「立ち退き請求書」を賃借人に送付します。この書面には、立ち退きの理由、希望する退去時期、立ち退き料の有無や金額などを明記します。
特に家賃滞納や契約違反が理由の場合、感情的な言葉を避け、事実関係を客観的に記述することが重要です。
手順②:話し合いは文書や録音で残しておく
直接交渉を行う際は、後のトラブルを避けるために文書や録音で記録を残しましょう。賃貸人側も誠実に交渉を進め、虚偽や隠し事を避けることが大切です。
手順③:退去手続きをする
賃借人との間で立ち退きに合意ができた場合は、立ち退き料の支払いや退去日の確定など具体的な手続きに移ります。合意に至らない場合、調停や裁判などの法的手段に訴える必要が生じる場合もあります。
立ち退きに必要な条件
賃借人に退去してもらうためには、以下の条件が必要です。
- 条件①:契約解除
- 条件②:更新拒絶
次項より、個別にみていきましょう。
条件①:契約解除
双方の合意に基づく契約解除、または家賃滞納や契約違反による信頼関係の崩壊が条件です。
一度の家賃滞納では契約解除が難しい場合もあり、家賃滞納の回数や頻度、対応履歴などを総合的に考慮して判断されます。
条件②:更新拒絶
契約期間終了の1年から6ヶ月前に更新拒絶の通知を行うのが一般的です。ただし、任意の更新拒絶は認められず、前述の「立ち退き要求が可能なケース」で挙げた正当な理由が必要です。
関連記事:賃貸物件の立ち退き交渉の進め方とは?チェックポイントや流れを解説
立ち退き交渉がうまくいかないときの対処法
借地借家法により賃借人の権利は強く守られているため、立ち退き要求が容易ではない場合もあります。裁判に発展した場合、法的な保護により賃貸人に不利な状況になりかねません。
立ち退き交渉に応じてもらえなかったり、賃借人と連絡がつかなかったりする場合の対処法は、以下のものが存在します。
- 弁護士に交渉代行を依頼する
- 裁判で立ち退きを求める
- 不動産を売却する
それぞれ、詳しくみていきましょう。
弁護士に交渉代行を依頼する
自分での交渉が難しい場合、不動産法に精通した弁護士に交渉を代行してもらうことが有効です。この方法なら、法律的な側面を考慮しつつ、感情的な対立を避けながら交渉を進められます。
裁判で立ち退きを求める
直接交渉での解決が困難な場合、裁判所に立ち退きを申し立てる手段もあります。この場合も、専門知識を持つ弁護士のサポートが不可欠です。
不動産を売却する
立ち退き交渉が困難で長期化することを避けたい場合、不動産を売却するという選択肢もあります。市場価格より低くなる可能性はありますが、交渉にかかるコストや時間を考慮すると有効な手段となり得ます。
弁護士に交渉代行してもらうメリットとデメリット
自分(賃貸人)自身で交渉することが難しい場合、弁護士に立ち退き交渉を代行してもらうという方法があります。その際のメリットとデメリットをご紹介します。
弁護士に交渉代行してもらうメリット
立ち退き交渉でトラブルになると、精神的ストレスや時間を費やしてしまいます。代行してもらうことで、これらの負担がなくなることはメリットといえます。
法律のプロである弁護士に代行してもらうことで、効率よく解決まで進められます。早く退去してもらうことができれば、新しい入居者を早く迎えられるでしょう。
家賃滞納によって立ち退きを要求する場合、退去させることはできても家賃の回収が難しい可能性があります。
しかし、弁護士に依頼することでそのときの状況に応じた適切な対処をしてくれるため、家賃回収が可能になる場合もあります。
裁判になってから弁護士に依頼するよりも、立ち退き交渉の段階で弁護士に代行をしてもらっていれば、訴訟がスムーズに進みます。訴訟への手続きなども代行でしてくれる場合があるため、労力の削減にもなるでしょう。
弁護士に交渉代行してもらうデメリット
弁護士に交渉代行をしてもらうことはメリットがある反面、デメリットもあります。弁護士に依頼をすると相談料や着手金・成功報酬などの費用が発生します。いくらかかるかは事務所によって異なるため、事前に確認しましょう。
弁護士を介入させることで賃借人からのイメージが悪くなり、関係性が悪化する可能性があります。立ち退き後も関係を良好に保ちたい場合は、よく検討するのが賢明です。
まとめ
「入居者が家賃を支払ってくれないから出て行ってほしい」「立ち退き要求をしているけれど、受け入れてもらえない」など、立ち退きに関してお困りの場合はプロに相談をするとよいでしょう。
交渉の段階から弁護士に依頼をすることで、穏便かつスムーズに解決することが期待できます。また、不動産自体を売却することで煩雑な契約関係やトラブルから脱却することも可能です。不動産業者に相談する、という方法も視野に入れてみてほしいと思います。
本ブログで情報発信を行っている「ワケガイ」は、訳あり物件を積極的に買い取っている専門業者です。所有物件についてお悩みの方は、訳あり物件の買取に特化したワケガイに、ぜひお問い合わせください。
| 運営団体 株式会社ネクスウィル 2019年1月29日設立。訳あり不動産の買取を行う不動産会社。相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産を買い取り、法的知識や専門知識を以って、再度市場に流通させている。 |