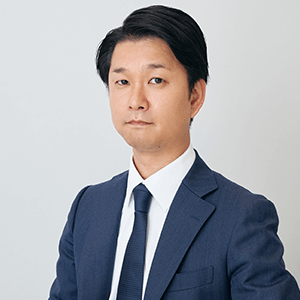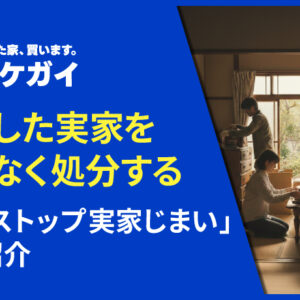について今すぐご相談できます。
お電話する
新築住宅の購入後、近隣トラブルや生活利便性の低さ、住宅ローンの返済負担など、さまざまな理由で後悔するケースが増えています。
新築住宅購入後の後悔は年々増加傾向にあり、購入者の多くが何らかの不満を抱えています。のような状況で選択肢となるのが、新築物件の売却です。
ただし、新築物件の売却には、住宅ローンの完済や税金の問題、適切な売却時期の見極めなど、さまざまな課題があります。
そこで本記事では、新築購入後の後悔の主な理由から、高値で売却するためのポイント、売却時の注意点まで、実践的な対処法を詳しく解説します。
目次
新築購入後に後悔する5つの主な理由
新築住宅の購入は人生の一大決心であり、慎重に選んだはずなのに、入居後にさまざまな理由で後悔する人は少なくありません。
主な理由としては、以下の5つが挙げられます。
- 理由①:近隣トラブルが原因で住みづらい
- 理由②:生活の利便性が思ったより低い
- 理由③:毎月のローン支払いが負担になる
- 理由④:間取りが理想と異なる
- 理由⑤:家の中の動線が悪い
それぞれ個別にみていきましょう。
理由①:近隣トラブルが原因で住みづらい
新築住宅で暮らし始めて最も多く聞かれる後悔は、近隣トラブルです。騒音やゴミの処理など、日常生活における摩擦が発生するケースは少なくありません。
特にマンションでは、上下階や隣室からの生活音が想定以上に響くことがあり、心理的なストレスの原因となるケースが目立ちます。
例えば、上階からの子どもの足音や、隣室からのペットの鳴き声など、事前には予測できなかった音の問題は深刻です。
共用部分の使い方を巡るトラブルも多く、ゴミの分別ルールを守らない住民がいることで、清潔な住環境が保てないといった悩みも寄せられています。
理由②:生活の利便性が思ったより低い
新築物件の価格を抑えるため、駅から離れた場所を選んだものの、実際の通勤・通学が予想以上に大変だと感じる人は多いのではないでしょうか。
例えば「バス停まで10分なら大丈夫」と思っていても、雨の日や荷物が多い日には負担に感じることもあるでしょう。
さらに、近隣の商業施設やスーパーマーケットまでの距離が遠いことで、日常の買い物にも不便を感じるケースがあります。
休日の外出も、電車やバスの本数が少ないために予定が立てにくく、理想としていた生活スタイルが実現できないというのが現状です。
理由③:毎月のローン支払いが負担になる
住宅ローンの返済は、長期にわたる大きな固定支出です。当初の計画では余裕があると考えていても、子どもの教育費や予期せぬ出費が重なり、返済が重荷になってくることがあります。
特に、近年は35年以上の長期返済が一般的になっているため、定年退職後も返済が続くケースが増えています。
年金生活になってからの返済は、当初の想定以上に厳しいものとなるでしょう。
理由④:間取りが理想と異なる
モデルルームや図面で見た印象と、実際に暮らしてみての感覚には大きな違いがあります。収納スペースの使い勝手が悪い、リビングの日当たりが想像と違うなど、生活を始めてから気付く不満は少なくありません。
理由⑤:家の中の動線が悪い
実際に生活を始めると、家事や育児で必要なスペースや動線が十分でないと判明するケースもあります。
「キッチンからリビングまでの距離が遠い」「洗濯物を干す場所までの動線が複雑」など、日々の生活で何度も往復する箇所の使い勝手の悪さは、大きなストレスとなりがちです。
新築に後悔した場合に取れる2つの選択肢
購入した新築住宅に住むことが難しくなった場合、一般的には「売却」「賃貸」の2択から選択することになるでしょう。
それぞれの選択肢には独自のメリットとデメリットが存在します。自分の状況に合わせて最適な選択をすることが大切です。
売却して新しい家に住み替える
新築住宅を売却する場合、売却金額で住宅ローンを完済できれば、新しい家への住み替えが可能になります。
住宅ローンの残債が売却額を下回るアンダーローンの状態であれば、比較的スムーズに住み替えの実現が見込めます。
ただし、新築の場合はオーバーローンになるケースが多く見られます。この場合、不足分は自己資金や別のローンで対応する必要があります。
住み替えローンの利用も検討に値しますが、現在の住宅ローンの残債と新しい住宅の購入資金を一本化するため、金融機関の審査が厳しくなる点に注意が必要です。
物件を売却できても、引き渡しができない状況に陥る可能性も考慮に入れておく必要があります。
賃貸に出して別の家に住む
新築住宅を賃貸物件として活用する道もあります。ただし、住宅ローンを利用している場合、金融機関に事前の確認が必要です。
住宅ローンは、基本的に本人が居住することを前提とした契約になっているため、無断で賃貸に出すとローンの一括返済を求められる可能性があります。
賃貸物件として利用する場合、この条件から外れるため、事前にローンを返済しておく必要があるのです。
なお、住宅ローンから賃貸用物件に利用可能なアパートローンへの移行を検討することも可能です。自己資金での住宅ローン返済が難しい場合は、金融機関に相談してアパートローンへの切り替えを検討することをおすすめします。
賃貸経営により定期的な収入を得られる一方で、空室リスクや維持管理の負担も発生することを忘れてはいけません。
新築を売るための手順
新築住宅を売却したいと考えた際、引き渡しまでの手順は大きく6ステップに分けられます。
- 手順①:不動産査定を依頼する
- 手順②:販売活動を開始する
- 手順③:購入希望者との交渉を進める
- 手順④:売買契約を締結する
- 手順⑤:引き渡し手続きを完了する
それぞれ個別に解説します。
手順①:不動産査定を依頼する
新築住宅の売却を成功させるためには、まず不動産の適正な価格を把握する必要があります。不動産会社に査定を依頼し、市場価格や類似物件の売却事例をもとに適切な売却価格を設定します。
複数の不動産会社に査定を依頼し、価格の妥当性や販売戦略を比較検討することがポイントです。
手順②:販売活動を開始する
査定価格が決まったら、販売活動を開始します。不動産会社と媒介契約を結び、インターネット広告、チラシ配布、オープンハウスの開催など、ターゲットに合わせた販売戦略を実施します。
販売活動を効果的に進めるためには、物件の魅力を最大限にアピールする写真や情報を整えることが重要です。
手順③:購入希望者との交渉を進める
販売活動を通じて購入希望者が現れたら、価格や引き渡し時期などの条件について交渉を行います。
価格交渉だけでなく、住宅ローンの審査状況や購入希望者の意向をしっかりと確認し、スムーズな取引を進めることが大切です。必要に応じて価格の見直しや条件調整を行う柔軟な対応が求められます。
手順④:売買契約を締結する
交渉が成立したら、売買契約を締結する必要があります。契約では、売却価格や引き渡し日、手付金の額、違約金などの重要な事項を明確にします。
契約締結時には、不動産会社の立ち会いのもと、重要事項説明が行われるため、契約内容を十分に理解し、疑問点は事前に確認しておきましょう。
手順⑤:引き渡し手続きを完了する
売買契約後、買主の住宅ローン手続きや必要書類の準備を進め、引き渡しに向けた準備を整えます。建物の最終確認(内覧)や登記手続き、残代金の受領、鍵の引き渡しを行い、正式に売却が完了します。
スムーズな引き渡しのために、引っ越しや公共料金の精算なども計画的に進めましょう。
新築の家を売却する際に発生する費用
新築住宅を売却する際には、さまざまな費用が発生します。売却価格から差し引かれる諸費用を事前に把握しておくことで、手元に残る資金を正確に見積もることが可能です。
主な費用としては、以下のとおり。
- 仲介手数料
- 登記関連費用
- 譲渡所得税
- 住民税
- 印紙税
- 住宅ローン完済手数料
上記について詳しくみていきましょう。
仲介手数料
これは不動産会社に売却の仲介を依頼する際にかかる費用で、法律により上限が決められています。手数料は売却価格に応じて計算され、一般的な上限は以下の通りです。
- 売却価格200万円以下:5.5%(税込)
- 200万円超400万円以下:4.4%(税込)
- 400万円超:3.3%(税込)
例えば、売却価格が3,000万円の場合、仲介手数料の上限は「(200万円 × 5.5%)+(200万円超400万円以下の部分 × 4.4%)+(400万円超の部分 × 3.3%)= 18万円 + 8.8万円 + 85.8万円 = 112.6万円(税込)」 となります。
不動産会社によっては手数料を割引するケースもあるため、複数社で比較するのがおすすめです。
登記関連費用
売主が負担する代表的な登記費用として、「抵当権抹消登記」があります。これは、住宅ローンを完済した後に、担保として設定されていた抵当権を法務局の登記簿から抹消する手続きです。
この手続きを完了しない限り、登記簿上は抵当権が残ったままとなり、売却やその他の手続きに支障が出る可能性があります。
①:登録免許税
抵当権抹消の際には、法務局へ登録免許税を納める必要があります。登録免許税は、対象となる不動産1件につき1,000円と定められています。
例えば、一般的な一戸建てで土地と建物の2つの登記がある場合、登録免許税は合計2,000円(1,000円 × 2件)かかります。また、土地が複数の筆に分かれている場合は、その筆数ごとに1,000円ずつ加算されます。
(参考:国税庁「登録免許税のあらまし」)
②:司法書士に支払う報酬
抵当権抹消登記の手続きを自分で行うことも可能ですが、登記申請書の作成や必要書類の整理など、専門知識が必要になるため、多くの人が司法書士に依頼しています。司法書士に依頼する場合、報酬として1万円~2万円前後が相場となります。
報酬額は依頼する司法書士事務所や地域によって異なり、手続きの難易度や物件数に応じて変動することがあります。例えば、登記する不動産が複数ある場合や、相続登記と合わせて依頼する場合などは、追加費用が発生することもあります。
譲渡所得税
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、その所得に対して所得税が課されます。所有期間によって税率が異なり、以下のように分類されます。
- 短期譲渡所得(所有期間5年以下):30.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%)
- 長期譲渡所得(所有期間5年超):15.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%)
ただし、自宅として利用していた場合、「3,000万円特別控除」が適用されると、売却益から3,000万円まで差し引くことができ、多くのケースで譲渡所得税が発生しません。
(参考:国税庁「短期譲渡所得の税額の計算/長期譲渡所得の税額の計算」)
住民税
不動産売却による利益には、住民税も課されます。こちらも所有期間によって税率が変わります。
- 短期譲渡所得(所有期間5年以下):9%
- 長期譲渡所得(所有期間5年超):5%
住民税は翌年の6月以降に自治体へ納付する形となります。特別控除が適用される場合は、譲渡所得税と同様に課税対象額を減らすことができます。
(参考:総務省「個人住民税」)
印紙税
不動産売買契約書を作成する際には、契約書に印紙を貼付し、消印することで印紙税を納める必要があります。これは、正式な売買契約書が課税文書に該当するためです。
印紙税の金額は、売買価格によって異なり、契約書に記載された売買金額が大きいほど税額も高くなります。
| 契約金額 | 印紙代 |
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1〜10万円 | 200円 |
| 10〜50万円 | 400円 |
| 50〜100万円 | 1,000円 |
| 100〜500万円 | 2,000円 |
| 500〜1,000万円 | 1万円 |
| 1,000〜5,000万円 | 2万円 |
| 5,000万〜1億円 | 6万円 |
| 1億〜5億円 | 10万円 |
| 5億〜10億円 | 20万円 |
| 10億〜50億円 | 40万円 |
| 50億〜 | 60万円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 |
(参考:国税庁「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」)
住宅ローン完済手数料
住宅ローンを完済する際、金融機関に手数料を支払う必要があります。手数料は金融機関によって異なりますが、一般的には以下の範囲となります。
- 繰り上げ返済手数料:3万円~5万円前後
契約内容によっては手数料が免除されるケースもあるため、事前に金融機関へ確認することをおすすめします。
新築の家をなるべく高く売却する方法
新築住宅を売却する際、なるべく高い価格で売却する上では以下のポイントを意識しましょう。
- 適切な売却価格を設定する
- 内覧時に良い印象を与えられるようにする
- 早めに販売活動を開始する
- 未使用状態を強調する
- 実績豊富な不動産会社に依頼する
次項より、詳しく解説します。
適切な売却価格を設定する
売却価格の設定は、スムーズな売却を実現する上では重要な要素です。近隣の取引事例や地域の相場を慎重に分析し、適正な価格を見極める必要があります。
価格設定が高すぎると買い手がつかず、売却期間が長引いて価格を下げざるを得なくなる可能性があります。
一方で、新築や築浅物件は資産価値が高い状態を保っているため、適切な価格設定をすることで購入時の価格に近い金額での売却も十分可能です。エリア特性や住宅の特徴を踏まえた戦略的な価格設定を行いましょう。
内覧時に良い印象を与えられるようにする
購入希望者の物件内覧は、売却の成否を左右する重要な機会です。特に新築や築浅物件を探している人は、清潔感や美観を重視する傾向にあります。
内覧時には、室内をできるだけ整理整頓し、清潔な状態を保つよう心がけましょう。
空気の入れ替えやこまめな掃除はもちろんのこと、生活感を抑えることも大切です。できれば専門業者によるハウスクリーニングを実施し、新築時の状態に近づけることをおすすめします。
また、キッチンや水回りの設備は特に丁寧に清掃し、メンテナンスの行き届いた印象を与えることが重要です。
早めに販売活動を開始する
新築住宅は、建築完了から時間が経過するほど資産価値が低下していく傾向にあります。売却を決断したら、できるだけ早く行動に移すことが賢明です。
特に、建築後1年以内で未入居の場合は「新築物件」として売り出すことができ、より高値での売却が期待できます。
さらに、不動産市況や金利の動向なども売却価格に影響を与えます。市場環境が良好なうちに売却活動を開始することで、より良い条件での売却につながる可能性が高まります。
未使用状態を強調する
建築後間もない物件の場合、未使用であることは大きな強みとなります。
水回りや設備機器がまったく使用されていない点や、内装材の新しさを積極的にアピールすることで、購入希望者の関心を高めることができます。
特に以下の点を重視して、物件の魅力を伝えましょう。
- 設備や内装材が新品同様の状態であること
- メーカー保証が十分に残っていること
- 住宅設備のメンテナンス履歴が皆無であること
- 新築時の品質が保たれていること
これらの要素を効果的にアピールすることで、新築物件としての価値を最大限に引き出すことができます。
実績豊富な不動産会社に依頼する
新築物件の売却には、特有のノウハウが必要です。新築や築浅物件の取り扱い実績が豊富な不動産会社を選ぶことで、適切な価格設定や効果的な販売戦略を立てることができます。
信頼できる不動産会社の特徴は以下のとおりです。
- 新築物件の売却実績が豊富
- 価格設定の根拠を明確に説明できる
- 物件の価値を最大限引き出す提案力がある
- 迅速で丁寧なコミュニケーションが取れる
特に重要なのは、査定額の根拠を具体的に説明できることです。近隣の取引事例や市場動向を踏まえた説得力のある説明ができる不動産会社を選びましょう。
新築を売却する際の注意点
新築住宅の売却には、以下のような注意点があります。
- 住宅ローンを利用しているなら完済が必要
- 売却時に税金が発生する場合がある
- 理由によって売却価格が下がる可能性がある
次項より、個別にみていきましょう。
住宅ローンを利用しているなら完済が必要
新築住宅のローンは残債が多く残っているのが一般的です。売却には住宅ローンの完済が必須となるため、売却金額だけでは返済が賄えないオーバーローンの状態になりやすいという特徴があります。
この場合、不足分を自己資金で補う必要があります。住み替えを予定している場合は、住み替えローンの利用も検討に値します。ただし、金融機関の審査基準は厳格で、返済計画の綿密な立案が求められます。
売却時に税金が発生する場合がある
新築住宅を売却して利益が出た場合、譲渡所得税が課されます。前述のとおり、税率は所有期間によって異なりますが、以下の条件を満たす場合、3,000万円特別控除の適用を受けられる可能性があります。
- 売却する家に住んでいた期間が通算1年以上あること
- 売却する年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えていること
- 売却後に同じ家を買い戻さないこと
- 売却先が親族などの特別な関係者でないこと
この控除を利用することで、税負担を大幅に軽減できる場合もあります。なお、一度も居住していない新築物件の場合は、この特例を利用できないため注意が必要です。
理由によって売却価格が下がる可能性がある
売却理由によっては、物件価格に大きな影響を与える場合があります。特に物理的な不具合や法律的な問題、心理的な瑕疵がある場合は、価格が下がりやすい傾向にあります。
売主には重要事項説明の一環として、物件の瑕疵を買主に説明する義務があります。雨漏りや事故の発生などを隠して売却すると、宅建業法違反となる可能性があるため、誠実な対応が求められます。
新築物件でお悩みの方は「ワケガイ」にご相談ください

当社(株式会社ネクスウィル)は、新築物件を含む「訳あり不動産」の買取に特化したサービス「ワケガイ」を提供しています。
新築購入後にさまざまな事情で売却を検討される方の中には、住宅ローンの返済や近隣トラブルなど、デリケートな課題を抱えているケースも少なくありません。
ワケガイでは、新築物件の売却においても、お客様の状況に応じた柔軟な対応が可能です。住宅ローンが残っている場合や、早急な売却が必要な場合でも、最短1営業日での買取査定、適正価格での買取をお約束します。
物件の価値を最大限に活かしながら、お客様の状況に寄り添った売却プランをご提案いたします。新築物件の売却でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
新築住宅の売却を検討する際は、まず複数の不動産会社に相談し、適切な市場価値の査定を受けることから始めましょう。その際、新築や築浅物件の取り扱い実績が豊富な不動産会社を選ぶことが重要です。
また、売却か賃貸かの判断は、現在の経済状況や将来の収入見込み、物件の立地特性などを総合的に検討して決める必要があります。特に住宅ローンが残っている場合は、金融機関への事前相談も欠かせません。
焦って判断せず、専門家のアドバイスを受けながら、最適な選択をしていきましょう。
運営団体 2019年1月29日設立。訳あり不動産の買取を行う不動産会社。相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産を買い取り、法的知識や専門知識を以って、再度市場に流通させている。 訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、空き家、訳あり不動産CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を展開。 経済界(2022年)、日刊ゲンダイ(2022年)、TBSラジオ「BOOST!」(2023年)、夕刊フジ(2023年)などで訳あり不動産について解説している。2024年度ベストベンチャー100選出。 これまでの買取の経験をもとに、訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』(代表取締役 丸岡・著)を2024年5月2日に出版。 |