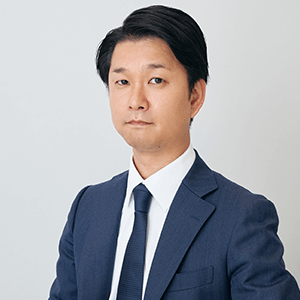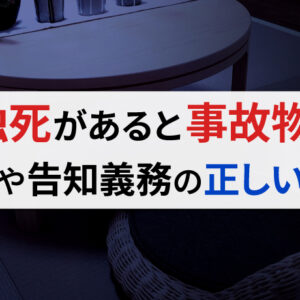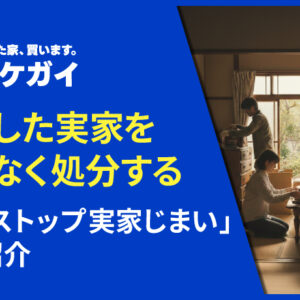について今すぐご相談できます。
お電話する
事故物件を所有していると、売却しようとしても価格が大幅に下がったり、買い手がなかなか見つからなかったりといった問題が発生します。
特に、自殺や事件が発生した物件は心理的瑕疵が大きく、通常の不動産市場では売却が難しくなるケースが少なくありません。その際に知っておくべきなのが事故物件の定義や価格相場、売却方法です。
事故物件とは、過去に死亡事故や事件などが発生し、購入希望者に心理的影響を与える可能性のある不動産を指します。
ただし、すべての死亡事故が事故物件として扱われるわけではなく、告知義務の有無や価格の下落幅はケースによって異なります。
そこで本記事では、事故物件の基本的な定義、ケースごとの価格相場、売却の際に知っておくべきポイントを詳しく解説します。
目次
そもそも事故物件とは?
事故物件とは、過去に死亡事故や事件が発生し、心理的瑕疵(かし)があるとされる不動産のことを指します。
ただし、すべての死亡事故が事故物件として扱われるわけではありません。売却や賃貸の際に告知義務が発生するかどうかは、事故の内容や発生場所によって異なります。
一般的に、室内での自殺や殺人事件、火災や水害による死亡事故などは、買い手や借り手にとって心理的抵抗が大きく、事故物件として扱われます。
一方で、老衰による自然死や、マンションの共用部分で発生した事故などは、告知義務が不要とされるケースもあります。
事故物件の売却を検討する際には、まず物件の状況を正しく把握し、どのような影響があるのかを理解しておくことが大切です。
事故物件で発生する告知義務とは
事故物件の売却や賃貸を行う際には、一定の条件下で「告知義務」が発生します。これは、過去に発生した死亡事故や事件について、買主や借主に対して事前に説明する義務のことです。
国土交通省のガイドラインでは、「事件性や自殺による死亡があった場合、原則として3年間は告知義務がある」とされています。
ただし、事故の種類や発生場所によって扱いが異なり、自然死や病死の場合は告知不要とされることが多々あります。また、一度売却や賃貸が成立し、次の取引に移行した場合は、告知義務がなくなるケースも存在します。
告知義務を怠ると、売却後に契約解除や損害賠償を求められることがあるため、事前に不動産業者と相談し、適切な対応をとりましょう。
【ケース別】事故物件の売却価格の相場はどのくらい?
事故物件の価格相場は、発生した事故の種類や経過年数によって大きく異なります。心理的瑕疵が強く影響するケースほど、価格が下がる傾向にありますが、すべての事故物件が極端に値下がりするわけではありません。
ここでは、具体的なケースごとの価格相場を解説します。
自然死・孤独死が発生した物件の相場
自然死や孤独死が発生した物件は、事故物件の中では比較的価格の下落幅が小さい傾向にあります。特に、家族に見守られながら亡くなった自然死であれば、市場価格にほぼ影響が出ないことが一般的です。
一方で、孤独死の場合は発見までの時間が影響を与えます。遺体の発見が遅れ、室内に臭いや汚れが残る場合は「特殊清掃」が必要になり、価格が10〜20%程度下がることもあります。
自殺があった物件の相場
自殺が発生した物件は、心理的瑕疵の影響が大きく、市場価格に対して20〜40%程度の値下がりが見られることが多々あります。特に、発生から3年以内の物件は事故物件として扱われ、買い手が見つかりにくくなります。
ただし、自殺から5年以上が経過し、すでに転売や賃貸契約が結ばれている場合は、心理的抵抗が薄れ、価格の影響が少なくなることもあります。
リフォームや間取り変更を行うことで、買い手の抵抗感を軽減し、売却価格を引き上げる方法も検討できます。
他殺・事件性のある物件の相場
殺人事件や暴力的な犯罪が発生した物件は、心理的瑕疵の影響が最も強く、市場価格に対して50%以上の値下がりが発生することが一般的です。
事件の内容が広く報道されていた場合や、地元住民の間で話題となった場合は、長期間にわたって市場価格が回復しにくい傾向があります。
このような物件を売却する際には、買取業者への売却や、用途変更(事務所・倉庫など)を検討するのがひとつの方法といえます。
通常の住宅市場では買い手が見つかりにくいため、専門業者に相談しながら適切な売却戦略を立てることが重要です。
火災や水害による事故物件の相場
火災や水害で大きな被害を受けた物件は、建物の損傷具合によって価格が大きく変動します。特に、建物が半焼・全焼したケースでは、建物の価値がほぼなくなるため、更地価格に近い価格での売却となることも多々あります。
一方で、構造体に問題がなく、修繕が可能な場合は、市場価格の30〜50%程度の値下げで売却できる可能性も高まります。
火災の場合は、事故の原因によっても価格に影響が出ます。失火による火災であれば比較的売却しやすいものの、放火や事件性のある火災では心理的瑕疵が強くなり、売却が難しくなることがあります。
事故物件の価格相場を調べる方法
事故物件を売却する際、適正な価格で取引するためには事前に相場を把握しておくことが重要です。市場価格を知らないまま売却を進めると、相場よりも低い価格で手放してしまう可能性があります。
相場を調べる方法としては、以下のとおり。
- 過去の事故物件の売却事例を確認する
- 不動産買取業者に査定を依頼する
- 事故物件専門のサイトやデータベースを活用する
- 一般的な不動産相場と比較して価格差を把握する
- 事故の種類や経過年数による価格変動を考慮する
次項より、個別にみていきましょう。
過去の事故物件の売却事例を確認する
事故物件の売却相場を知るためには、過去の類似物件の取引事例を確認することが有効です。
特に、同じエリアや似た条件の物件の成約価格を調べることで、自身の物件の相場を把握しやすくなります。
売却事例は、不動産情報サイトや事故物件専門のデータベース、または不動産会社の成約事例レポートなどを通じて確認できます。
ただし、個別の事情によって売却価格が異なることもあるため、複数の事例を比較しながら参考にすることが大切です。
不動産買取業者に査定を依頼する
事故物件の正確な売却相場を把握するには、不動産買取業者に査定を依頼するのが効果的です。買取業者は市場の動向を熟知しており、物件の状況に応じた適正価格を提示してくれます。
査定には「簡易査定」と「訪問査定」の2種類があります。簡易査定はオンラインや電話で行うため手軽ですが、正確な価格を知るには訪問査定を受けるのが望ましいです。
特に、事故物件は心理的瑕疵の影響が大きいため、詳細な査定を受けた上で売却計画を立てることをおすすめします。
事故物件専門のサイトやデータベースを活用する
近年では、事故物件の情報を集約した専門サイトやデータベースも充実しており、これらを活用することで相場を調査できます。
代表的なものとして、「大島てる」などの事故物件情報サイトがあります。このようなサイトでは、事故の発生場所や内容を確認できるため、同じ地域の類似物件がどのように扱われているのかを調べる手がかりになります。
ただし、売却価格の詳細までは掲載されていないことが多いため、他の方法と併用することが望ましいです。
一般的な不動産相場と比較して価格差を把握する
事故物件の価格は、通常の不動産と比べてどの程度下がるのかを知ることが重要です。近隣の同条件の一般物件と比較し、事故物件の価格差を把握することで、適正な売却価格を設定しやすくなります。
一般的に、事故物件の価格下落率は以下のような傾向があります。
- 自然死・孤独死:10〜20%
- 自殺:20〜40%
- 他殺・事件:50%以上
- 火災・水害:30〜50%
これらを参考にしながら、自分の物件の適正価格を見極めていくことが大切です。
事故の種類や経過年数による価格変動を考慮する
事故物件の価格は、事故の発生からの経過年数によって変動します。心理的瑕疵が強く影響する物件は、事故直後は市場価格が大幅に下落しますが、時間の経過とともに影響が薄れていく傾向があります。
一般的には、事故発生から3年以内は価格が大きく下がるものの、5年以上経過すると心理的影響が薄まり、市場価格に近づくことが多いです。
ただし、事件性が強く、ニュースなどで広く知られている物件は、長期間にわたり影響を受けることがあります。
事故物件の売却は専門業者への直接買取依頼がおすすめ!
事故物件を早期に売却したい場合や、一般市場での売却が難しい場合には、専門の買取業者に直接売却する方法がおすすめです。
買取業者は、通常の仲介売却とは異なり、買主を探す必要がないため、短期間で確実に売却できます。
専門業者に買取を依頼する際の手順としては、以下のとおりです。
- 利用手順①:買取業者をリサーチして選ぶ
- 利用手順②:査定を依頼し、価格の相場を把握する
- 利用手順③:複数の業者と比較し、条件を交渉する
- 利用手順④:契約内容を確認し、売買契約を締結する
- 利用手順⑤:売却後の手続きや税金の確認を行う
次項より、個別に解説します。
利用手順①:買取業者をリサーチして選ぶ
事故物件を買取業者に売却する際は、信頼できる業者を選ぶことが最も重要な要素です。
業者によって買取価格の設定基準や対応の柔軟性が異なり、選び方を誤ると適正な価格で売却できない可能性があります。
まず、買取実績が豊富な業者を探しましょう。過去の取引件数や事故物件の取り扱い経験が多い業者は、適正な査定を行い、スムーズな取引が期待できます。
公式サイトに買取実績が掲載されている業者をチェックし、売却事例を確認するとよいでしょう。
また、業者の信頼性を確認するために、口コミや評判を調べることも大切です。Googleのレビューや不動産系の口コミサイトで、実際に買取を依頼した人の評価を参考にすると、業者の対応の良し悪しが分かります。
ただし、すべての口コミが正確とは限らないため、複数の情報源を確認することが重要です。
利用手順②:査定を依頼し、価格の相場を把握する
買取業者を選んだら、次に行うのが査定の依頼なります。査定を受けることで、物件の市場価値や売却価格の目安を把握でき、適正価格での売却に繋げられます。
査定には、「簡易査定」と「訪問査定」の2種類があります。
- 簡易査定(机上査定):オンラインや電話で物件情報を伝えるだけで、大まかな査定額を算出してもらう方法。
- 訪問査定:業者が実際に物件を訪問し、建物の状態や事故の影響を詳細に確認した上で査定を行う方法。
査定の際には、事故の内容や物件の状態を正直に伝えることが重要です。隠してしまうと、後に契約トラブルになる可能性があるため、正確な情報を提供しましょう。
査定を依頼する際は、1社だけでなく、最低でも2~3社に依頼し、提示された価格を比較することをおすすめします。
利用手順③:複数の業者と比較し、条件を交渉する
査定結果が出たら、すぐに契約するのではなく、複数の業者を比較し、より良い条件で売却できるよう交渉することが大切です。業者ごとに査定額や買取条件が異なるため、慎重に検討しましょう。
比較するポイントとして、以下の項目をチェックするとよいでしょう。
- 買取価格の違い(数十万円~数百万円の差が出ることもある)
- 売却スピード(即日対応の業者もあれば、数週間かかる業者もある)
- 諸費用の負担(契約書作成費や登記費用など、業者が負担してくれるかどうか)
- 契約の柔軟性(キャンセルが可能か、引き渡し時期の調整ができるか)
利用手順④:契約内容を確認し、売買契約を締結する
売却先が決まったら、売買契約の締結を行います。契約前には、契約内容を細かく確認し、トラブルを防ぐことが大切です。
特に、以下の項目は事前にチェックしておきましょう。
- 売却価格と支払い条件(一括払いか分割払いか、支払い時期はいつか)
- 契約解除の可否(契約後にキャンセルが可能か、違約金の有無)
- 売却後のトラブル対応(告知義務違反などのリスクはないか)
- 引き渡しのスケジュール(売却後すぐに退去が必要か、一定期間住み続けられるか)
利用手順⑤:売却後の手続きや税金の確認を行う
売却が完了したら、それで終わりではありません。売却後に発生する税金や手続きを確認し、適切に対処することが必要です。
売却後に必要な手続きとして、以下の点を押さえておきましょう。
- 税金の支払い:売却によって利益(譲渡所得)が出た場合、譲渡所得税や住民税が発生する。譲渡所得がある場合は、翌年の確定申告が必要。
- 確定申告の準備:売却価格が購入価格を上回った場合、確定申告を行い、必要な税金を納める必要がある。
- 売却後の資金計画:売却益が出た場合、次の不動産購入や生活資金の確保など、計画的に資金を運用することが大切。
また、売却後に契約内容に関するトラブルが発生しないよう、売却時の契約書類や支払い明細をしっかり保管しておくことも重要です。
事故物件を高く売却するためのポイント
事故物件の売却価格は、事故の種類や発生からの経過年数によって大きく変動します。しかし、適切な準備をすることで、通常よりも高い価格での売却が可能になることもあります。
具体的な工夫のポイントとしては以下のとおりです。
- 市場価格を調査しておく
- 実績の多い業者を選ぶ
- 修繕や清掃を行い、物件の印象を改善する
- 売却方法(買取・仲介)を比較し、最適な選択をする
それぞれ個別に解説します。
市場価格を調査しておく
市場価格を調査する方法として、以下のような手段があります。
- 過去の事故物件の売却事例を調べる(不動産取引サイトや専門データベースを活用)
- 不動産会社や買取業者の査定を受ける(複数の業者に査定を依頼して比較する)
- 通常の不動産相場と比較する(事故物件による価格下落率を考慮)
特に、近隣の同条件の物件と比較し、どの程度の価格差があるのかを把握することが重要です。
実績の多い業者を選ぶ
事故物件の売却は、通常の不動産とは異なる専門知識が求められます。そのため、取引実績が豊富な業者を選ぶことが重要です。
経験の浅い業者では、査定額が適正でなかったり、売却までに時間がかかったりする可能性があります。
実績のある業者を選ぶ際には、以下のポイントを確認しましょう。
- 事故物件の買取・仲介実績が豊富か
- 過去の成約事例を提示してくれるか
- 売却までのスピード感があるか
- 口コミや評判が良いか
特に、事故物件を専門に扱う買取業者は、市場の動向を理解しているため、適正価格での買取が期待できます。
修繕や清掃を行い、物件の印象を改善する
事故物件は、買い手の心理的抵抗が強いため、適切な修繕や清掃を行うことで、売却価格を引き上げることができます。特に、事故の痕跡をできるだけ目立たなくすることが重要です。
改善策として、以下のような方法があります。
- ハウスクリーニングを実施し、臭いや汚れを除去する
- 壁紙や床材を張り替え、事故の痕跡をなくす
- リフォームや間取り変更を行い、別の用途として使えるようにする
ただし、大規模なリフォームを行うと、売却価格よりも修繕費が高くなる可能性があるため、コストと効果を考慮しながら対応することが大切です。
売却方法(買取・仲介)を比較し、最適な選択をする
事故物件の売却方法には、大きく分けて「買取」と「仲介」の2つがあります。それぞれメリット・デメリットがあるため、自分の状況に応じて最適な方法を選ぶことが重要です。
| メリット | デメリット | |
| 直接買取 | 短期間で確実に売却できる | 相場より価格が安くなりやすい |
| 仲介による売却 | 高く売れる可能性がある | 買い手が見つかるまで時間がかかる |
事故物件は市場での流通が難しいため、仲介で売却する場合は専門知識のある不動産会社を選ぶことが重要です。一方、確実に売却したい場合は、買取業者を利用するのが適した選択肢となります。
事故物件の売却ではどのような費用が発生する?
事故物件を売却する際には、さまざまな費用が発生します。具体的には、以下のものが挙げられます。
- 売却前に発生する費用(修繕・クリーニング・測量費など)
- 買取業者への売却時にかかる諸費用(手続き費用・登記費用など)
- 売却後に発生する税金(譲渡所得税・住民税など)
それぞれ個別に解説します。
売却前に発生する費用(修繕・クリーニング・測量費など)
事故物件は、売却前にある程度の修繕や清掃を行うことで、買い手の心理的抵抗を和らげることができます。ただし、費用対効果を考え、必要な範囲のみにとどめることが大切です。
修繕費(※破損や老朽化がある場合)
物件の破損や老朽化が進んでいる場合、最低限の修繕を行うことで売却価格を引き上げることができます。特に、壁紙の張り替え、床の補修、設備の交換などは、比較的低コストで印象を改善できるため、検討するとよいでしょう。
ハウスクリーニング費
通常の使用による汚れを落とし、室内を清潔な状態に保つために必要な費用です。特に長期間空き家だった場合や、タバコやペットの臭いが染みついている場合は、プロのクリーニングを依頼することで、売却しやすくなります。
特殊清掃費(※事件・自殺・孤独死などの場合)
事件や自殺が発生した物件では、血液や体液の除去、消臭・除菌作業が必要になることがあります。このような特殊清掃の費用は数万円~数十万円かかることが一般的です。
測量費(※境界が不明確な場合)
土地の境界が不明確な場合や、買主から測量を求められた場合にかかる費用となります。測量の内容によりますが、一般的には10万~50万円程度の費用がかかることがあります。
インスペクション費(※建物の状況を確認する場合)
買主が安心して購入できるよう、事前に建物の状態を確認するための費用です。シロアリ被害や構造上の問題がないかを調べることで、スムーズな売却につながります。費用は5万~10万円程度が一般的です。
買取業者への売却時にかかる諸費用(手続き費用・登記費用など)
買取業者への売却では、仲介手数料がかからないためコストを抑えられる一方で、契約や登記に関連する費用が発生することがあります。
契約書作成費
売買契約書の作成にかかる費用です。通常、不動産会社が作成するため売主側で負担することは少ないですが、必要に応じて専門家に依頼すると費用がかかることがあります。
所有権移転登記費
物件の名義を買主(買取業者)に変更するために必要な登記費用です。手続きを司法書士に依頼する場合は、5万~10万円程度が一般的な相場となります。
登録免許税
登録免許税は、不動産の所有権移転登記を行う際に発生する税金です。この税額は、固定資産税評価額に一定の税率をかけて計算されます。
通常、売買による所有権移転登記の税率は2%とされています。しかし、2026年(令和8年)3月31日までに登記を行う場合、軽減措置が適用され、税率が1.5%に引き下げられます。
また、契約内容によっては、この税金を買取業者が負担することもあります。特に、買取業者が「登記関連の費用をすべて負担」と明示している場合、売主側の負担なしで売却できるケースもあるため、契約時に確認しておくとよいでしょう。
(参考:国税庁「登録免許税の税額表」)
抵当権抹消費(※住宅ローンが残っている場合)
売却する物件に住宅ローンが残っている場合、抵当権を解除するための手続きが必要です。登録免許税は1,000円~2,000円(1筆あたり)で、司法書士に依頼する場合は1万~3万円程度の報酬が発生します。
司法書士報酬(※登記手続きを依頼する場合)
登記手続きを専門家に依頼する場合にかかる費用です。2万~5万円程度が相場ですが、登記内容や地域によって異なります。
売却後に発生する税金(譲渡所得税・住民税など)
事故物件を売却して利益(譲渡所得)が発生した場合、税金が課される可能性があります。それぞれ個別にみていきましょう。
譲渡所得税
売却によって得た利益(譲渡所得)に課税される税金です。計算式は以下のとおり。
- 譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 売却時の諸費用)
税率は所有期間によって異なり、5年以下の短期譲渡所得は39.63%、5年以上の長期譲渡所得は20.315%となります。
(参考:国税庁「短期譲渡所得の税額の計算/長期譲渡所得の税額の計算」)
住民税
譲渡所得が発生した場合、住民税の支払いも必要です。税率は短期譲渡所得で9%、長期譲渡所得で5%と定められています。
確定申告費(※税理士に依頼する場合)
譲渡所得が発生した場合、翌年の確定申告が必要になります。税理士に依頼する場合は5万~10万円程度の報酬がかかることがあります。
その他税金(※相続物件の場合の相続税など)
相続した物件を売却する場合、相続税が発生するケースも存在します。ただし、相続税の申告期限(相続開始から10か月以内)を過ぎていれば、売却時には追加の相続税はかかりません。
「ワケガイ」なら訳あり物件も短期で買取可能!

当社(株式会社ネクスウィル)は、訳あり物件の買取に特化したサービス「ワケガイ」を提供しています。通常の市場では売却が難しい事故物件についても、最短1日で買取が可能な体制を整えています。
事故物件は心理的瑕疵が影響し、一般的な売却ルートでは買い手が見つかりにくいのが現実です。特に、自殺や事件のあった物件は、価格が大きく下がるだけでなく、仲介業者に断られることも少なくありません。
しかし、当社では専門の買取スキームを活用し、迅速かつ適正な価格での買取を実現しています。
また、手続きの負担を軽減するため、売主様の費用負担を最小限に抑えるサポートも行っていますので、お気軽に無料査定をご活用ください。
まとめ
事故物件の売却を検討する際は、物件の定義や告知義務を正しく理解し、適切な方法で売却を進めることが重要です。
すべての死亡事故が事故物件になるわけではなく、事故の種類や発生場所によって告知義務の有無が変わるため、まずは自分の物件がどのように扱われるのかを確認しましょう。
また、売却価格の相場は、事故の種類や経過年数によって大きく変動します。売却前には市場価格を調査し、適正な価格で売るための準備を進めることが大切です。
さらに、事故物件を高く売却するには、修繕や清掃を行い、買い手の心理的抵抗を軽減する工夫も有効。
売却を急ぐ場合は、事故物件の買取実績が豊富な業者を選び、複数の査定を比較することをおすすめします。適切な判断をすることで、より良い条件での売却が可能になります。
運営団体 2019年1月29日設立。訳あり不動産の買取を行う不動産会社。相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産を買い取り、法的知識や専門知識を以って、再度市場に流通させている。 訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、空き家、訳あり不動産CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を展開。 経済界(2022年)、日刊ゲンダイ(2022年)、TBSラジオ「BOOST!」(2023年)、夕刊フジ(2023年)などで訳あり不動産について解説している。2024年度ベストベンチャー100選出。 これまでの買取の経験をもとに、訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』(代表取締役 丸岡・著)を2024年5月2日に出版。 |