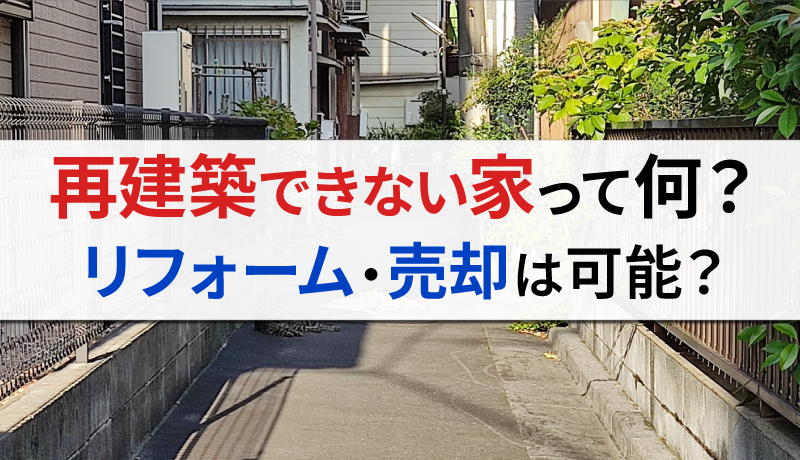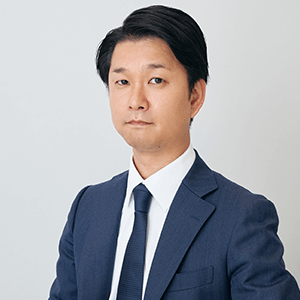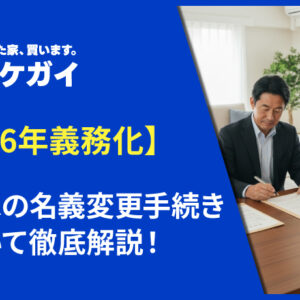こんにちは。ワケガイ編集部です。
再建築不可物件を相続した場合や購入を検討している場合、「建て替えができず将来価値が下がる」「売却が難しい」といった問題が発生します。その際に知っておくべきなのが再建築不可物件の基本知識です。
再建築不可物件とは、建築基準法の接道義務を満たさないために新築や増築が制限されている土地付き建物を指します。リフォームや活用方法にも制約があり、購入後に思わぬ不便を感じるケースも少なくありません。
そこで本記事では、再建築不可物件の定義や条件、メリット・リスク、活用方法や再建築可能にするための手段まで詳しく解説します。
について今すぐご相談できます。
お電話する
目次
再建築不可物件とは?定義や条件を解説
再建築不可物件と聞くと「古い家が建て替えられない土地」という印象を持つ方が多いでしょう。しかし、実際には明確な法的基準があり、その条件を満たさないと再建築が認められません。まずは、どのような土地が再建築不可と判断されるのか、その基本的な条件を押さえておく必要があります。
再建築不可物件の条件
再建築不可物件と判断される大きな理由は、建築基準法で定められた「接道義務」を満たしていないことにあります(例:「土地が接している道路の幅が4メートルに満たない場合」「敷地が道路に接している部分(間口)が2メートル未満しかない場合」など)。
こういったケースでは、建て替えが認められず「再建築不可」となります。
さらに、そもそも接している道が建築基準法上の「道路」と認められていないケースもあります。私道や農道、昔からある細い小道などは、そのままでは法律上の道路と見なされず、結果として再建築不可の扱いになることがあります。
見た目には普通の土地でも、こうした法的要件をクリアしていなければ新たに家を建てられません。判断する際は、以下の条件をまず確認することが大切です。
<再建築不可物件とされる主な条件>
- 接する道路の幅が4メートル未満である
- 土地の間口(道路に接する部分)が2メートル未満である
- 接している道が建築基準法上の道路として認められていない
(参考:e-Gov 法令検索「建築基準法」)
再建築不可物件の例
再建築不可物件は、特定の条件が重なる土地に多く見られます。見た目では判断しづらいケースもあるため、典型的なパターンを押さえておくと理解しやすくなります。
| 種類 | 内容 |
| 旗竿地(はたざおち) | 細い通路を通って敷地に入る土地。通路幅が2メートル未満だと接道義務を満たさず、建て替えできない。 |
| 袋地(ふくろち) | 四方を他の土地に囲まれ、道路に一切接していない土地。法律上の道路にアクセスできず、再建築不可となる。 |
| 古い住宅が密集する地域 | 昭和25年の建築基準法制定前に建てられた住宅が多いエリア。昔の基準のまま建てられたため、現行法では再建築不可扱いになる場合がある。 |
こうした物件は地方都市や古い町並みに多く、価格が安い理由の多くは「建て替えができないこと」にあります。購入や相続を検討する際は、必ずこうした点を確認しましょう。
再建築不可かどうかを調べる方法
自分の土地や購入予定の物件が再建築不可かどうかを確認するには、役所で調べるのが確実です。
市区町村の建築指導課などの窓口で、土地の住所を伝えれば接道義務を満たしているかどうかを教えてくれます。あわせて登記簿謄本や公図、測量図などを持参すると判断がスムーズです。
最近は自治体のホームページで「道路台帳」や「指定道路図」を公開しているところもあり、インターネット上で確認できる場合もあります。
ただし、ネットでの確認は専門的な知識がないと判断が難しいため、最終的には窓口で確認する方が確実です。不動産会社に依頼して調べてもらうこともできるので、購入前に必ず確認しておきましょう。
<再建築不可かどうか調べる方法まとめ>
- 市区町村役所の建築指導課に相談する
- 登記簿謄本や公図、測量図を用意して確認する
- 自治体のホームページで道路台帳・指定道路図を確認する
- 不動産会社に依頼して専門的な判断をしてもらう
関連記事:再建築不可物件の調べ方とは?必要書類や再建築できない場合の対応方法を解説
再建築不可物件のメリット
再建築不可物件というと「建て替えができない」というマイナスのイメージが先行しがちですが、視点を変えれば魅力もあります。
最も大きなメリットは購入価格の安さです。一般的な土地や建物と比べると、再建築不可物件は半値近い価格で売り出されることも珍しくありません。そのため、限られた予算で物件を探す人や、立地を優先して住まいを選びたい人には選択肢が広がります。
さらに、固定資産税などの維持コストが比較的低い点も挙げられます。土地の評価額が低く抑えられるため、毎年の税負担が軽く、所有し続けても家計の圧迫が少ないのです。
建物の状態が良ければ、住みながら賃貸部分を運用したり、駐車場や倉庫として貸し出して収益化することも可能でしょう。
用途に制約はあるものの、工夫次第でコストを抑えながら価値を引き出せるのが再建築不可物件の面白さでもあります。価格や税金の軽さを前向きにとらえれば、他の物件にはない使い方を見つけるきっかけになるでしょう。
再建築不可物件のリスク
再建築不可物件は購入価格の安さなどの利点もありますが、長期的に所有したり売却を考えたりする段階になると、特有のリスクが重くのしかかります。
建て替えが認められないという根本的な制約があるため、資産価値や活用の幅に限界が生まれます。特に大きなリスクとしては、以下の4つです。
- リスク①:建て替えができず資産価値が低い
- リスク②:災害で全壊すると再建築が不可能
- リスク③:ローン審査が厳しく融資が難しい
- リスク④:売却時に買い手が見つかりにくい
それぞれ個別にみていきましょう。
リスク①:建て替えができず資産価値が低い
再建築不可物件の最大の問題は、建て替えが認められないことによる資産価値の低さです。通常の土地は古い建物を解体して新しい住宅を建てれば価値が維持されますが、再建築不可ではそれができません。
結果として市場での評価は低く、価格も大幅に下がる傾向があります。特に住宅地の場合、新築需要を取り込めないため買い手は限定され、長期的な投資資産としては不安定です。
所有するだけなら税金が安いというメリットもありますが、「資産として育てられない土地」という現実を受け入れる必要があります。
リスク②:災害で全壊すると再建築が不可能
再建築不可物件は、もし地震や台風などの災害で全壊した場合、新しい建物を建てられません。部分的な修理や補修であれば許可されることが多いですが、倒壊して基礎からやり直す必要が出ると法律上の制約が発生します。
つまり、一度の大きな災害で「住める家」を失う可能性があり、その土地は空き地のまま使い道がなくなる恐れもあるのです。自然災害の多い日本においては、このリスクを軽く見ることはできません。
リスク③:ローン審査が厳しく融資が難しい
再建築不可物件を購入する際、金融機関の住宅ローンを利用するのも簡単ではありません。銀行にとって担保価値の低い土地への融資はリスクが高く、融資自体を断られるケースも少なくないのです。
仮にローンが組めても「金利が高く設定されたり、自己資金の多さを求められたりと、条件が厳しくなりがちです。現金購入できる層や投資目的の買い手にしか売れないことも、このリスクを助長しています。
リスク④:売却時に買い手が見つかりにくい
再建築不可物件は売却しづらいという問題もあります。建て替えができない土地を欲しがる人は限られており、一般的な住宅購入層はまず候補から外されてしまいます。
最終的に購入を検討するのは投資家や専門業者などごく一部で、提示価格よりさらに値引きを求められることも少なくありません。
売れ残った結果、管理コストだけがかかり続けるという状況に陥ることもあります。売却を視野に入れるなら、時間と値下げが必要になる可能性も考えられます。
再建築不可物件そのままでの活用例
再建築不可物件は建て替えができないため、価値が低いと考えられがちです。しかし、発想を変えれば「今ある建物や土地をそのまま使う」という選択肢もあります。
改築を前提としない活用なら、法律上の制約も少なく、初期投資を抑えながら収益化することも可能です。ここからは、再建築不可物件を解体せずに使う代表的な活用例見ていきましょう。
- 活用例①:駐車場やバイク置き場として貸し出す
- 活用例②:倉庫やトランクルームとして利用する
- 活用例③:貸し店舗やアトリエとして活用する
- 活用例④:賃貸住宅としてそのまま運用する
次項より、詳しく解説します。
活用例①:駐車場やバイク置き場として貸し出す
土地の形や立地がよければ、駐車場やバイク置き場として貸し出すのが最も手軽な活用方法です。特に住宅街や駅の近くなど車両需要の高いエリアでは、数台分のスペースでも安定的な利用者が見込めます。
大規模な工事をしなくても、砂利敷きや簡易舗装程度で貸し出しを始められるため、初期費用が少なく済むのも魅力です。月極駐車場や時間貸しのコインパーキングとして運用することもでき、相場より安く貸し出しても一定の収益が期待できます。建物を解体しなくても「土地の部分」を活かせる点で、非常に現実的な選択肢といえます。
活用例②:倉庫やトランクルームとして利用する
古い建物を取り壊さず、倉庫やトランクルームとして活用する方法もあります。荷物の一時保管場所や資材置き場を探す人や業者は多く、需要は安定しています。
建物に多少の老朽化があっても「人が住むための基準」ほど厳しい修繕を求められないため、費用を抑えて貸せるのが利点です。場合によっては個人向けのトランクルームとして貸し出すこともでき、小規模でも収入源になるでしょう。住宅としては価値が低い再建築不可物件でも、用途を変えれば十分に役立つケースです。
関連記事:再建築不可物件の新たな活用法!コンテナハウスで資産価値を高める方法をご紹介
活用例③:貸し店舗やアトリエとして活用する
再建築不可の古い建物をリノベーションして、小さな貸し店舗やアトリエに活用する事例も存在します。ギャラリー、雑貨店、工房、サロンなど、少人数で利用する業態にはぴったりでしょう。
築年数のある建物特有の雰囲気を活かすことで、魅力的な空間として利用者を引きつけることもできます。大掛かりな改装が難しい再建築不可物件でも、内装の調整や最低限の修繕で店舗利用は十分に可能でしょう。
住居として再評価されない物件でも、別の角度から価値を引き出せます。
活用例④:賃貸住宅としてそのまま運用する
建物の状態が良ければ、再建築不可物件でもそのまま賃貸住宅として貸すことが可能です。築年数の古い家は家賃を相場より安く設定する必要がありますが、低家賃で住める物件は需要があります。
単身者や短期入居者、高齢者など、価格を重視する層がターゲットになりやすいです。もちろん、居住用に貸す場合は最低限の修繕や安全確認が求められますが、初期投資を抑えつつ収入を得られる方法です。
再建築不可物件は活用の幅が狭いといわれますが、建物の状態を活かせば収益化は十分見込めるでしょう。
再建築不可物件ってリフォーム・売却は可能?
再建築不可物件は「建て替えができない」という制約が最大の特徴です。では、既存の建物を直したり、いざという時に売ったりすることはできるのでしょうか。
答えは「リフォームはある程度可能」「売却もできるが容易ではない」です。ここからは、再建築不可物件におけるリフォームの現実と、売却の難しさについて詳しく見ていきます。
リフォームについては修繕・改修は可能だが増改築は制限される
再建築不可物件でも、内装のリフォームや屋根・外壁の補修といった「建物を直す工事」は基本的に認められています。具体的には以下のとおりです。
<再建築不可物件で可能なリフォーム例>
- キッチンや浴室、トイレなどの水回り設備の交換
- 屋根の葺き替えや外壁の塗り直し
- 床や壁紙などの内装リフォーム
- 給湯器やエアコンなど住宅設備の更新
住みやすさを維持するための工事なら、ほとんど制約なく行えます。
一方で、、大きな間取り変更や増築、建物の高さを変えるような工事となると話は別です。これらは「建て替え」に近い扱いになり、接道義務を満たしていない土地では許可されません。
特に、建物を一度解体して新しい基礎を作るようなリノベーションは事実上できないと考えてよいでしょう。つまり、快適に暮らすための改修はできても、大掛かりな工事で価値を高めることは難しいというのが現実です。
関連記事:再建築不可の物件のリフォームはどこまでできる? リフォーム時の注意点もあわせて解説
売却も可能だが非常に難しい
再建築不可物件は売却自体はできますが、かなり苦戦すると思われます。買い手は建て替えができないリスクを理解しているため、価格は大きく下がりますし、一般的な住宅購入者はまず候補に入れません。
最終的に購入を検討するのは「専門の不動産業者」「再建築不可物件を投資目的で扱う人」など、ごく限られた層にとどまります。
また、金融機関が住宅ローンを出しにくいことも売却の障害になります。ローンを使えないと、現金で購入できる人しか買えないため、さらに買い手が絞られるのです。
売却するなら、時間をかける覚悟や、想定より大きな値引きが必要になるでしょう。つまり「売ることはできる」が、条件や相場を理解して慎重に進めましょう。
関連記事:再建築不可の物件が売れない原因とは?建て替えができない不動産の売却方法を解説
再建築不可物件のリフォーム・売却に影響が出た「2025年の建築基準法改正」とは?
2025年に行われた建築基準法改正は、住宅を建てる際の安全性や耐震性をより強く求める内容でした。
特に、これまで審査を簡略化できた小規模住宅にも厳格な構造審査が義務付けられた点が大きな変化です。これにより、既存の「再建築不可物件」にも波及する影響が出ています。
とくに注目されるのは「4号特例」という制度の縮小です。
この特例は、一定の小規模建築物であれば建築確認申請の際に構造計算を省略できる仕組みでした。これが見直され、より広い範囲で詳細な審査が必要になりました。結果として、再建築不可物件であっても、内装のリフォームや増築、さらには売却時の評価にも影響が出る可能性が高まっています。
(参考:国税庁「改正建築基準法について」)
4号特例が縮小された理由
4号特例が縮小された理由は、老朽化した住宅の増加と、耐震性不足による安全面の不安が深刻化していたためです。
長年の使用で劣化した建物が全国に多く残り、地震や台風の被害時には小規模住宅の倒壊や損壊が相次ぎました。本来であれば構造審査が必要なケースでも、4号特例によって簡略化されたまま建てられた建物が災害に弱いとの指摘が相次いだのです。
この社会的背景を受け、2025年の建築基準法改正では安全性を最優先に、特例を狭めて審査を強化する方向に舵が切られました。
結果として、これまで簡単に通っていたリフォームや増築も詳細な審査や書類提出が必要となり、コストや時間の負担が増えています。再建築不可物件を扱ううえで、制度変更による影響を無視できない状況になったといえるでしょう。
再建築不可物件を「再建築可能」にするための方法
再建築不可物件でも、条件を満たせば再び建物を建てられる「再建築可能」な土地に変えられる場合があります。
そのための方法はいくつかあり、法律や制度をうまく活用することで道が開けます。ここでは、代表的な5つの手段を紹介します。
- 隣地を購入して接道義務を満たす
- 敷地設定で隣地と一体化する
- セットバックで建築基準法に適合させる
- 43条但し書き申請で特例許可を取る
- 50戸連たん制度(一部地域限定の救済措置)を活用する
以下より、個別にみていきましょう。
隣地を購入して接道義務を満たす
最も直接的で効果的なのは、土地に面する道路までの間口を広げるために隣地を買い足す方法です。現在の土地が道路に1.5メートルしか接していない場合、隣地を一部購入し2メートル以上にすれば接道義務をクリアできます。
購入価格や交渉の難しさはありますが、確実性が高い手段です。成功すれば、将来的に建て替えも可能となり、資産価値の大幅な改善が期待できます。
敷地設定で隣地と一体化する
隣地を「購入」するのではなく、持ち主同士が合意して土地を一体利用する方法もあります。これを「敷地設定」と呼び、親族が所有する隣地と敷地設定を行えば、登記上は別々でも建築基準法上はひとつの土地とみなされ、接道義務を満たせる可能性があります。
売買を伴わないため費用が抑えられますが、隣地所有者の理解や将来の売却時の取り扱いなど慎重に合意形成を行う必要があります。
関連記事:再建築不可物件を建て替え可能にする「敷地設定」とは? メリットとデメリットや注意点を解説
セットバックで建築基準法に適合させる
土地に面した道路が幅4メートル未満の場合は、道路の中心線から2メートル後退して建物を建てる「セットバック」という方法があります。これにより、将来的に道路が4メートル幅とみなされ、接道義務を満たせることがあります。
土地の一部を事実上「道路提供」するため建築面積が減るデメリットはありますが、費用負担が比較的小さいため、現実的な選択肢として多く活用されています。
関連記事:セットバックって何?物件を再建築可能な状態にするための手順を解説
43条但し書き申請で特例許可を取る
建築基準法第43条には「但し書き」という規定があり、一定の条件を満たせば道路に接していない土地でも建築が認められる特例があります。これを役所に申請し、審査を通れば建て替えが可能になるケースがあります。
ただし、消防車や救急車が進入できるか、安全面の基準を満たしているかなど、厳しい確認が行われます。許可が下りれば再建築への道が開けますが、行政との調整が必要なため手間がかかります。
(参考:e-Gov 法令検索「建築基準法」)
関連記事:再建築不可物件の救済処置「43条但し書き」の概要をわかりやすく解説!
50戸連たん制度(一部地域限定の救済措置)を活用する
地方の一部では「50戸連たん制度」という救済措置があります。これは、周囲に50戸以上の家が連続して建っている区域で、幅員が4メートル未満の道でも建築が許されるという仕組みです。主に市街化調整区域などで適用され、役所の確認と申請が必要です。
エリアが限られているため使える人は限られますが、該当すれば再建築不可物件を再建築可能にする有効な手段になります。
再建築可能になった後の売却手順
隣地購入やセットバックなどで再建築不可物件が「再建築可能」になれば、資産としての価値は大きく変わります。建て替えができる土地として市場に出せるようになるため、買い手の幅も広がり、価格も見直されます。しかし、売却するには適切な準備と段階的な手続きが求められます。
具体的には、以下の4ステップです。
- 手順①:再建築可能になったことを確認し証明書類を取得する
- 手順②:不動産会社に査定を依頼する
- 手順③:媒介契約を結び売却活動を開始する
- 手順④:買主と売買契約を締結する
それぞれ個別にみていきましょう。
手順①:再建築可能になったことを確認し証明書類を取得する
まず大切なのは、「再建築可能になった」という事実を正式に証明できる書類を整えることです。接道義務を満たすために隣地を購入した、セットバックを行った、43条但し書きの許可を取得したといった経緯を証明するため、市区町村の建築指導課などで関連書類を発行してもらいます。
これらは売却時に買主や不動産会社が確認する重要な根拠資料になります。証明が曖昧なままだと、せっかく再建築可能になった土地でも「本当に建て替えられるのか」と不安視され、売却が難航する恐れがあります。
まずは書類を揃え、客観的に価値を示せる状態に整えましょう。
手順②:不動産会社に査定を依頼する
次に、不動産会社に査定を依頼します。再建築可能になったことで価値が上がっているため、再建築不可時の査定額より高い価格がつく可能性があります。複数の会社に査定を頼み、提示額だけでなく得意な販売エリアや売却実績を比較すると良いでしょう。
再建築不可から再建築可能になった経緯をきちんと説明し、書類を添えておくと、査定担当者も価格の根拠を示しやすくなります。査定段階で「建築可能であること」を強くアピールできれば、後の売却活動でも買主への説得材料になります。
手順③:媒介契約を結び売却活動を開始する
査定を経て依頼する会社を決めたら、媒介契約を結びます。専属専任媒介、専任媒介、一般媒介など契約の種類がありますが、それぞれ販売力や情報公開の範囲が異なります。
<媒介契約の種類と特徴>
- 専属専任媒介:1社だけに依頼する契約。自分で見つけた買主とも直接取引できず、業者がすべて対応。販売力は最も高い。
- 専任媒介:こちらも1社限定だが、自分で見つけた買主と直接契約できる。販売力と柔軟性のバランスが取れた契約。
- 一般媒介:複数の会社に依頼でき、自分でも売却活動ができる。情報は広がりやすいが、業者側の販売意欲はやや下がる傾向あり。
どの契約にするかは、売却スピードや自分の関与度合いに応じて選ぶとよいでしょう。
契約後は不動産会社が広告掲載や内覧対応を進め、再建築可能になったという点を買主に伝えてくれます。売主側も、問い合わせがあった際に補足資料を提示できるよう準備を整えておくことが大切です。
手順④:買主と売買契約を締結する
買主が見つかれば、価格や条件を調整したうえで売買契約を結びます。再建築不可から再建築可能になった経緯や取得した証明書は、このタイミングでも確認されます。
買主がローンを組む場合、金融機関もこれらの書類を重視するため、提出がスムーズにできるよう事前に整理しておきましょう。
契約締結後は決済・引き渡しを経て売却が完了します。書類が整っていれば、取引全体が円滑に進み、再建築可能になった価値をしっかり反映した価格で売却しやすくなります。
「ワケガイ」なら再建築不可物件も短期で買取可能!

当社(株式会社ネクスウィル)は、訳あり不動産の買取に特化したサービス「ワケガイ」を提供しています。再建築不可物件は、建て替えができないという理由で市場での流通が難しく、買い手がつかずに困っている所有者も少なくありません。
ワケガイでは、こうした一般的な不動産会社では扱いづらい物件も積極的に査定し、全国対応でスピーディに買い取ります。
状況によっては最短1日での現金決済にも応じており、手間をかけずに物件を手放せるのが強みです。売却が難しい土地や建物を抱えて悩んでいる方は、まずお気軽に無料査定をご活用ください。
事故物件に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 再建築不可物件は2025年にどうなる?
2025年の建築基準法改正で、4号特例が縮小されました。これにより、小規模住宅でも構造審査が必要になり、再建築不可物件のリフォームや増築がこれまで以上に難しくなる可能性があります。
Q2. 再建築不可物件はなぜ買うのか?
価格が安いため、倉庫や駐車場として使うなど、用途を割り切って購入する人が多いです。投資家や専門業者が買い取り、再建築可能にする工夫をして再販するケースもあります。
Q3. 再建築不可物件は最終的にどうなる?
老朽化が進むと、修繕費がかさみ、利用価値がさらに下がることがあります。状況によっては放置され空き家化することもありますが、早期に売却したり、再建築可能にして活用する選択肢もあります。
まとめ
再建築不可物件は、通常の物件より購入価格や固定資産税が安いという利点がある一方で、「建て替えができない」という根本的な制約が資産価値を大きく下げます。老朽化すれば修繕費の負担が増え、災害で全壊すれば新築もできず、土地自体の利用価値が限られてしまうリスクもあります。
しかし、接道義務を満たす工夫や43条但し書き申請などの制度を活用すれば、再建築可能に変えることも可能です。そうした取り組みが難しい場合でも、修繕して貸し出す、駐車場として使うなど現状のままで収益化する方法もあります。
相続や購入の段階で放置せず、「そのまま保有するのか、再建築可能化を目指すのか、早めに売却するのか」 を見極めることが大切です。
迷うと管理コストや税負担だけが積み重なりますので、建築や不動産の専門家の意見を早めに取り入れ、自分の資産にとって最も損のない行動を計画的に進めましょう。
運営団体 2019年1月29日設立。訳あり不動産の買取を行う不動産会社。相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産を買い取り、法的知識や専門知識を以って、再度市場に流通させている。 訳あり不動産の買取サービス「ワケガイ」、空き家、訳あり不動産CtoCプラットフォーム「空き家のURI・KAI」を展開。 経済界(2022年)、日刊ゲンダイ(2022年)、TBSラジオ「BOOST!」(2023年)、夕刊フジ(2023年)などで訳あり不動産について解説している。2024年度ベストベンチャー100選出。 これまでの買取の経験をもとに、訳あり不動産の解説をする著書『拝啓 売りたいのに家が売れません』(代表取締役 丸岡・著)を2024年5月2日に出版。 |