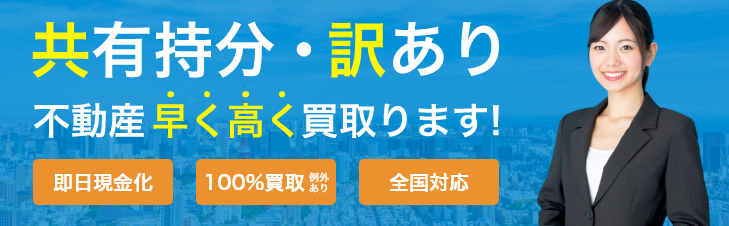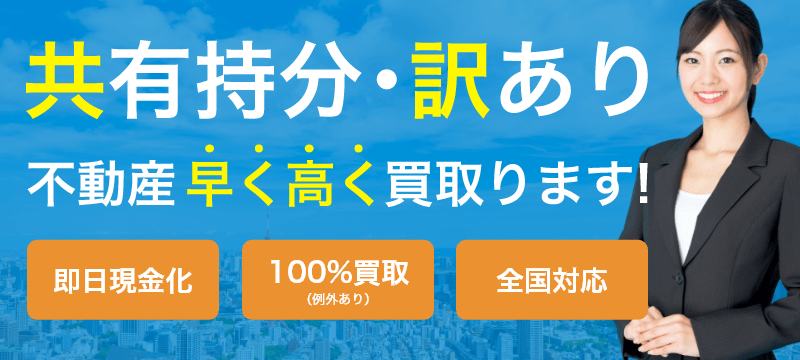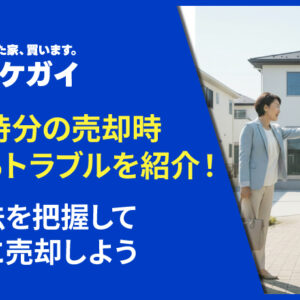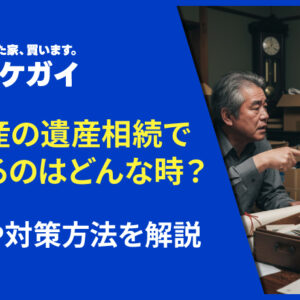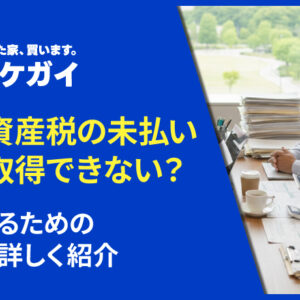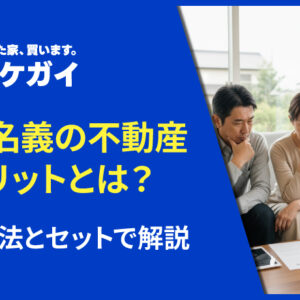こんにちは。ワケガイ編集部です。
相続や離婚、共同購入などで不動産を複数人で所有することになった際、「共有持分と区分所有の違いがよくわからない」「どちらの状態なのか判断できない」と戸惑われる方が少なくありません。
これらはどちらも複数人での所有形態ですが、権利のあり方や活用の自由度に大きな差があります。その違いを曖昧なままにしてしまうと、「知らないうちに不利な立場になっていた」「処分しようとしたら共有者の同意が必要だった」といったトラブルにもつながりかねません。
そこで本記事では、共有持分と区分所有の違いを整理し、それぞれの特徴や注意点を分かりやすく解説します。
目次
共有持分とは
共有持分とは、1つの不動産を複数人で所有する際に、それぞれが持っている「権利の割合」を示すものです。不動産の特定の場所(例えば1階部分や北側の部屋など)を物理的に分けて所有しているわけではなく、全体に対して「◯分の◯」という形で権利を持っている状態です。
たとえば、ある家族が遺産として家を相続し、兄弟3人で均等に分けることになった場合、それぞれの相続人が不動産全体に対して「3分の1」の共有持分を持つことになります。この場合、3人全員が家全体に対して権利を持つため、売却や修繕などを行うには、原則として他の共有者との協議が必要です。
関連記事:共有持分とは?不動産を共有し続けるリスクや共有状態の解消方法を解説
共有持分権とは
共有持分権は、財産を複数人で共有する際に、各個人が持つ持分やそれに伴う様々な権利を指します。この権利は、具体的な物理的所有物というよりは、不動産全体に対する割合の権利として抽象的な概念です。
不動産の共有は一般的に、夫婦や親子、兄弟間での購入、または相続によるもの。特に、夫婦でのマイホーム購入や、相続による賃貸物件の共有が典型的な例です。
共有持分の所有者(共有者)に認められる権利
共有者が有する権利は、以下のように分けられています。
- 変更(処分)行為
- 管理行為
- 保存行為
次項より、詳しくみていきましょう。
変更(処分)行為
共有不動産の物理的または法的な変更・処分を行う際には、共有者全員の同意が必要です。過半数の賛成があっても、一人でも反対する場合、行為を実行することはできません。
【変更(処分)行為の例】
- 売却
- 贈与
- 長期賃貸借
- 増築・改築
- 大規模修繕
- 抵当権の設定
- 取り壊し
- 建て替え
- 分筆/合筆
管理行為
共有不動産の管理行為には、共有者の持分割合の過半数の同意が必要です。例えば、3人の共有者がそれぞれ1/3の持分を持つ場合、2人が同意することで管理行為を行うことができます。
これは、民法第252条により、「共有者の管理に関する事項は、前条の場合を除き、共有者の持分数に応じて、その過半数で決する」と定められています。
(参考:e-Gov 法令検索「民法」)
【管理行為の例】
- 賃貸借契約の締結
- 不動産の共同利用方法の決定
- 賃料の減額
- 賃貸借契約の終了
関連記事:共有持分の管理行為とは?できること・できないことと対処法をわかりやすく解説
保存行為
共有物に関しては、各共有者が単独で「保存行為」を行うことが許されています。これは他の共有者に不利益をもたらさない範囲で行われ、他の共有者の同意は必要ありません。民法においても、各共有者が保存行為を自由に行えると認められています。
【保存行為の例】
- 修繕
- 無権利者に明渡し請求、抹消登記請求
- 法定相続による所有権移転登記
以上のように、不動産の共有者は上記のような権利を持っています。単独では意思決定ができないため「各共有者がお互いの権利を制限し合っている」と認識しましょう。
関連記事:共有している不動産の「保存行為」は単独で行える? 具体例と注意点を紹介
区分所有とは
区分所有とは、分譲マンションなど、複数の部屋に分かれた建物において、各部屋を個別に所有することを指します。このような部屋の所有者を「区分所有者」と呼び、建物自体は「区分所有建物」と称されます。
区分所有では、各部屋(専有部分)を単独で所有するだけでなく、建物全体の共用部分や、その建物が立つ土地(敷地)については、他の区分所有者と「共有持分」として共同で権利を持つという仕組みになっています。
つまり、共有持分は、区分所有に付随する権利のひとつとして位置づけられるものです。
区分所有建物は「区分所有法(正式名称:建物の区分所有等に関する法律)」に基づいて定められた要件を満たすものであり、各部屋に所有権を設定することによって成立します。(参考:e-Gov 法令検索「建物の区分所有等に関する法律」)
区分所有建物は「専有部分」と「共用部分」から構成され、分譲マンションの各戸が専有部分、階段やエントランスなどが共用部分となります。専有部分の所有者は共用部分を共有し、その持分割合は専有部分の床面積割合に基づいて決定されます。
敷地権とは
敷地権は、区分所有建物が立つ敷地と建物を一体として登記することで、敷地の権利と建物の権利を分離できないようにする権利形態です。敷地権化された建物において、区分所有者は専有部分の割合に応じた土地利用権(敷地利用権)を持ちます。
1984年の不動産登記法の改正以前、マンションは建物と土地を別々に登記しており、多くの問題が発生しました。
そのため、敷地権という権利形態が導入され、建物と土地を一体で登記することにより、登記上のミスが減少しました。敷地権は登記手続きを簡素化するために作られた概念であり、区分所有者が敷地利用権を通じて建物と土地を切り離して処分は行えません。
古いマンションは敷地権が設定されていないケースもある
1983年に区分所有法が改正され、敷地権が制定された背景から、1983年以前に建築されたマンションの中には敷地権が設定されていないケースも存在します。これらのマンションでは敷地権の設定がなくても売買取引は可能ですが、トラブルの原因となるリスクが伴います。
区分所有者に認められる3つの所有権
区分所有している場合、所有者は以下の権利を有します。
- 専有部分の所有権
- 共有部分の共有持分
- 土地の共有持分
それぞれ、詳しく解説します。
専有部分の所有権
専有部分とは、基本的に住居部分を指し、天井・壁・床に囲まれた内部空間を含みます。各区分所有者はこの専有部分について自由に使用・修繕・売却などを行う権利を持っています。
ただし、バルコニーや玄関ドア、窓といった部分は、建物全体の外観や安全性に影響を及ぼすため、専有部分には含まれず「専用使用部分」として分類されます。これは見た目には個人の所有物に見えても、他の所有者と共有しているという前提があるからです。リフォームなどを行う際には管理規約や管理組合の承認が必要になる場合もあるため、注意が必要です。
共有部分の共有持分
共有部分は、エントランスや階段、エレベーターなど、全ての区分所有者によって利用される部分です。これには電気や水道の設備も含まれる場合があり、管理規約によってはその範囲が限定されることもあります。
区分所有者は、これらの共有部分に対して持分を持ち、通常は各区分所有者の専有部分の床面積割合に基づいて決定されますが、管理規約によって異なる持分割合が設定されることもあります。
土地の共有持分
土地の共有持分、すなわち「敷地利用権」は、専有部分を支える土地の使用権を意味します。建物の利用には土地の使用権が不可欠であり、区分所有者はそれぞれがこの権利を持っていることになります。
多くの場合、敷地権の設定がされており、専有部分の名義変更時には敷地利用権の名義も同時に変更されます。
共有持分と区分所有、どちらが自由に使える?整理・活用のしやすさで見る違い
共有持分と区分所有は、いずれも不動産を複数人で所有する形式ですが、実際の運用には大きな違いがあります。共有持分は他の所有者と利害が絡み合う場面が多く、意思決定に制約が生じやすい一方、区分所有は専有部分の範囲が明確で、比較的自由に活用・処分しやすいという特徴があります。
下表では、主な3つの観点から両者を比較しました。ご自身の物件の状況と照らし合わせながら、適切な対応を検討する際の参考にしてください。
| 所有形態 | 自由度 | 整理のしやすさ | 売却のしやすさ |
| 共有持分 | 他の共有者の同意が必要な場面が多く、自由度は低い | 協議や裁判を要する場合があり、複雑になりやすい | 市場での流通が難しく、買い手が限られる傾向がある |
| 区分所有 | 専有部分は原則として自由に使え、意思決定しやすい | 単独での名義変更が可能で整理しやすい | マンション市場が確立しており、一般に売却しやすい |
共有持分は、自由度や整理のしやすさ、売却のしやすさのいずれにおいても、区分所有と比べて制約が多く、扱いにくい傾向があります。とくに、他の共有者との関係性や利害が絡むことで、物件の活用や売却に時間と手間がかかるケースが少なくありません。
そのため、共有状態にストレスや限界を感じている場合は、「そもそも共有を続けるべきか?」という視点で見直してみるのも一つの選択肢です。必要に応じて、持分の整理や売却など、抜本的な対処を検討することが、長期的には負担を軽減する近道になるかもしれません。
やっかいな共有状態の解消方法
共有状態が続くと、意思決定のたびに他の共有者の同意が必要になり、売却や活用が思うように進まないケースも少なくありません。とくに関係性が希薄な相続共有や、長年連絡が取れていない共有者がいる場合などは、将来的に不動産の価値を活かせなくなるリスクもあります。
こうした共有不動産の悩みを解消する上では、以下のような対策が有効です。
- 共有持分の売却(買取・第三者への売却)
- 共有持分の交換・譲渡などによる整理
- 共有物の分割(現物分割・換価分割・代償分割)
次項より、個別に解説します。
共有持分の売却(買取・第三者への売却)
共有状態を解消する方法として、まず検討されるのが「自分の持分を売却する」ことです。理想は他の共有者に買い取ってもらうことですが、感情的な対立や経済的な事情でそれが難しいことも多く見られます。その場合は、第三者に売却するという選択肢もあります。
ただし、共有持分だけを買いたいという人は限られているため、一般的な不動産市場では売却しづらいのが現実です。こうした背景から、共有持分の買取に特化した専門業者を活用するケースも増えています。相場に近い金額であれば、トラブルを避けて早期に手放す手段として有効です。
関連記事:共有持分の売却相場っていくら?価格の決まり方も交えて解説
関連記事:共有持分の高額買取業者の選び方とは? 買取相場や価格査定のポイントも解説
共有持分の交換・譲渡などによる整理
「共有している不動産が複数ある」「不動産以外の資産(預貯金など)と合わせて調整できる」といった状況であれば、持分の交換や譲渡によって、共有状態を整理することができます。
たとえば、兄弟で複数の不動産を共有している場合、「兄は土地Aの単独所有に、弟は土地Bの単独所有に」といった形で分け合うことが可能です。
こうした方法は、当事者間での信頼関係が一定程度あることが前提になりますが、お互いが納得できる解決を目指すうえでは、比較的円満なアプローチといえます。
関連記事:共有持分の「交換」とは?共有関係を解消する方法を詳しく解説
関連記事:共有持分を譲渡する3つの方法とは?注意点も交えて易しく解説
共有物の分割(現物分割・換価分割・代償分割)
話し合いによる解決が難しい場合には、法的な手続きによって共有状態を解消することも可能です。これが「共有物分割請求」と呼ばれる方法で、民法256条により認められた正当な権利です。
(参考:e-Gov 法令検索「民法」)
- 現物分割:土地を分筆して、それぞれが単独で所有する形にする方法。
- 換価分割:不動産を売却し、得た代金を持分割合で分ける方法。
- 代償分割:共有者の一人が他の共有者の持分を金銭で買い取ることで、単独所有を実現する方法。
いずれの分割も、まずは協議が必要ですが、話し合いがまとまらない場合には家庭裁判所に調停や訴訟を申し立てて決着を図ることもできます。最終的にどの手段が現実的か、費用や時間、関係性などを踏まえて慎重に判断することが重要です。
共有不動産でお悩みの方は「ワケガイ」にご相談ください!

当社(株式会社ネクスウィル)は、共有持分や訳あり物件の売却に特化したサービス「ワケガイ」を提供しています。
「共有名義の不動産を売りたくても話が進まない」「相続後の権利関係が複雑すぎて動けない」といったお悩みは、実は多くの方が抱える共通の問題です。ワケガイでは、共有持分のみのご相談にも対応しており、弁護士や司法書士など専門家との連携によって、売却や名義整理まで一貫してサポートしています。
売るべきか、共有を解消すべきか悩まれている段階でも構いません。まずはお気軽に無料査定をご活用ください。
まとめ
共有持分と区分所有はいずれも複数人で不動産を所有する形式ですが、その運用性や出口戦略には大きな違いがあります。共有持分は他の所有者との合意がなければ意思決定ができず、売却や活用が難航するケースも存在します。
一方で、区分所有は専有部分に限れば単独での利用・処分が可能で、管理や売却の自由度も比較的高いといえます。
もし、現在の不動産の所有形態に不便さやストレスを感じているのであれば、自身の権利構造を見直し、今後の活用や整理の方針を検討することが有益です。必要に応じて専門家の力を借りながら、共有状態を続けるのが本当に適切かどうか、冷静に判断しましょう。