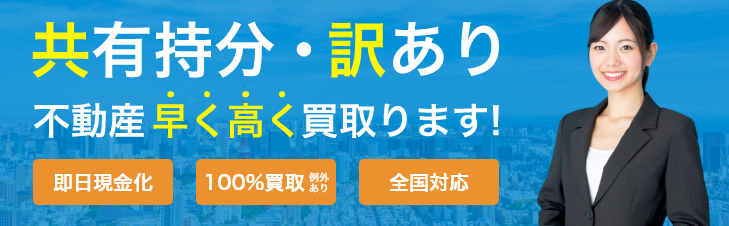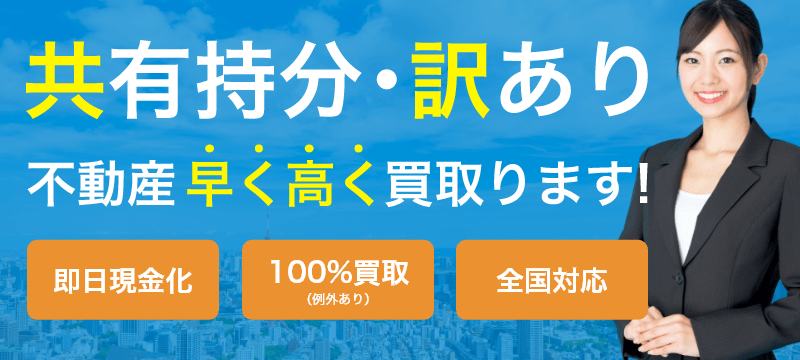相続や共同購入によって不動産を共有する場合、意思決定がスムーズに進まなかったり、共有者の高齢化や相続によって持分が分散したりするなど、管理や処分に大きな支障が出ることがあります。
その際に有効なのが「家族信託」です。家族信託とは、自身の不動産や共有持分を信頼できる家族に託し、契約に基づいて管理・処分してもらう仕組みを指します。
共有者が認知症になった場合や、将来的な承継まで見据えておきたい場合にも活用されています。
本記事では、共有持分の家族信託について、仕組みやメリット・デメリット、締結手続き、他の制度との比較まで、具体例を交えて丁寧に解説します。
目次
家族信託とは
家族信託とは、財産を持つ人(委託者)が信頼できる家族(受託者)に対し、財産の管理・運用・処分を任せる制度です。受託者は、あらかじめ定めた契約内容に従って財産を扱い、得られた利益は指定された人(受益者)が受け取ります。
たとえば、不動産を共有している家族が将来の管理や相続に備え、あらかじめ信託契約を結ぶことで、判断能力の低下や相続時のトラブルを回避しやすくなります。
従来の遺言や成年後見制度では対応が難しい部分をカバーできる点も大きな特徴です。信託の設計次第で、柔軟かつ長期的な資産管理が可能となります。
家族信託を構成する3つの当事者
家族信託は、次の3者によって構成されます。各者の役割と注意点は以下のとおりです。
| 立場 | 役割 | 注意点 |
| 委託者 | 自分の財産(不動産や預金など)を信託する契約の当事者 | 契約後は財産の名義が受託者に移るため、信託内容を誤ると想定外の結果になりうる。 |
| 受託者 | 委託者から託された財産を管理・処分する実務担当者 | 誠実に管理を行う法的義務(善管注意義務)があり、適任者の選定が重要。 |
| 受益者 | 信託財産から発生する利益を受け取る人(例:賃料や売却代金の配分など) | 遺留分や相続の扱いに配慮が必要。契約内容が不明確だと将来的に紛争を招くこともある。 |
信託契約を締結する際は、この3者の関係性や責任の範囲を具体的に定めておくことが欠かせません。
たとえば、「不動産の売却は誰の判断で可能とするか」「信託の終了条件をどうするか」といった実務面まで落とし込んで設計することで、後のトラブルを回避できます。
特に共有持分を信託する場合、相続や処分に関するルールを明文化することが、将来的な混乱を防ぐうえで有効です。
共有持分で家族信託を締結することは可能?
共有持分についても、家族信託の対象とすることは信託法上および民法上、合法かつ実務的に可能です。
信託法では、不動産を含む財産を信託契約により管理・処分の対象とすることが認められており(信託法第2条・第3条)、共有持分もこれに含まれます。
また、民法第251条では、各共有者が自分の持分を他人に譲渡することができると定められており、この持分の処分に信託契約を用いることにも、法的な障害はありません。
(参考:e-Gov 法令検索「民法」)
したがって、たとえば相続で取得した不動産の「自分の持分だけ」を家族信託の対象とし、信頼できる家族に管理を委ねるといった運用も可能です。
ただし、信託の効力が及ぶのはあくまで「信託契約の当事者の持分のみ」であり、他の共有者の権利や管理権限に直接影響を与えることはできません。たとえば、共有物の売却や建て替えといった共有者全体の合意が必要な行為については、信託により単独で意思決定ができるようにはなりません。
そのため、共有持分を信託する際は、他の共有者との関係性や合意形成の可能性も視野に入れた設計が求められます。
共有持分の家族信託を検討すべきシチュエーション例
ここからは、共有持分の信託についての具体的な活用例をみていきましょう。
- 例①:共有者間の意思決定が進まなくなった
- 例②:共有者の高齢化で判断能力が不安定になった
- 例③:将来的に相続で共有者が増えることが確定した
それぞれ個別に解説します。
例①:共有者間の意思決定が進まなくなった
共有名義の不動産を所有していると、「売却したい人」と「賃貸を続けたい人」など意見が割れる場面が多く見られます。
このような場合、全員の同意が得られなければ管理や処分が一切進まないというリスクがあります。家族信託では、あらかじめ信頼できる共有者などを受託者に指定し、契約で管理権限を委ねることにより、スムーズな意思決定を可能にすることができます。
例②:共有者の高齢化で判断能力が不安定になった
共有者の高齢化が進むと、認知症や判断能力の低下によって法的な合意が困難になる恐れがあります。そうなると、修繕や売却といった重要な手続きが一切できなくなる可能性も出てきます。
家族信託を活用すれば、元気なうちに管理権限を信頼できる人へ移しておくことができ、万が一の際にも財産の運用や処分が滞らずに済みます。
関連記事:共有名義人が認知症になったら、不動産は売却可能?成年後見人制度とセットで解説
例③:将来的に相続で共有者が増えることが確定した
相続によって不動産を複数人で共有するケースはよくありますが、さらにその後の二次相続が起きると、共有者の数が倍増することも少なくありません。
関係者が増えることで合意形成はさらに難しくなり、いわゆる「塩漬け不動産」となるリスクが高まります。こうした事態を避けるためには、事前に信託を組み、財産の管理・承継方針を明確にしておくのが現実的な選択肢です。
関連記事:共有持分は相続するべき?分割方法やトラブルの回避方法を解説
共有持分の家族信託を締結するメリット/デメリット
共有持分の家族信託は、煩雑な意思決定を一本化できる点で非常に有効な選択肢です。ただし、契約設計や運用には注意点もあり、実行にあたっては慎重な判断が求められます。以下に、主なメリットとデメリットを整理してご紹介します。
メリット
共有持分の信託を活用する最大のメリットは、共有者ごとの同意を必要とせず、受託者に管理権限を集中できる点です。
これにより、物件の賃貸や修繕、さらには売却などの判断を迅速に行うことが可能となります。共有者間で意見が分かれた場合でも、あらかじめ定めた信託契約に基づき、受託者が一定の裁量で判断できるため、合意形成の難航による機会損失を防げます。
また、前述のとおり認知症などによる判断能力の低下が発生しても、信託契約に基づく管理体制が維持されるため、不動産が“宙に浮く”事態を避けることができます。さらに、次世代の受益者を事前に設定しておくことで、相続発生後も持分が分散せず、円滑な承継と管理が実現しやすくなります。
デメリット
一方で、家族信託の活用にはいくつかの注意点も存在します。
まず、信託契約の設計には法律や税務に関する専門的な知識が求められ、弁護士や司法書士などの専門家の関与が前提となります。契約内容を曖昧にしたまま実行すると、後々のトラブルにつながるリスクも否定できません。
また、契約締結時には一定の費用が発生し、登記変更や受託者への報酬、管理に伴う実務的な手間も考慮する必要があります。さらに、設定内容によっては、法定相続人の遺留分を侵害するおそれがあり、相続人間での紛争に発展する可能性もあります。
こうした点を踏まえると、家族信託は非常に有効な制度である反面、「制度をどう設計するか」がその成否を大きく左右すると言えるでしょう。
共有持分の家族信託を締結するまでの流れ
共有不動産に家族信託を導入するには、法律や不動産の専門知識を要する手続きが伴います。しかし、流れ自体は明確で、以下のように4つのステップで整理できます。
- 手順①:信託の目的と関係者の意向を整理する
- 手順②:専門家と相談しながら信託契約を設計する
- 手順③:必要書類を揃えて記入する
- 手順④:法務局へ登記申請を行う
次項より、個別にみていきましょう。
手順①:信託の目的と関係者の意向を整理する
最初のステップは、「なぜ家族信託を行いたいのか」「誰に管理を託すのか」「誰に利益を還元したいのか」といった基本方針を明確にすることです。
たとえば、「父の持分を長男に管理してもらいたい」「いずれは孫へ承継したい」など、将来的な方向性を含めて整理しておくと、以降の設計がスムーズに進みます。
手順②:専門家と相談しながら信託契約を設計する
次に、司法書士や弁護士、税理士といった専門家の助言を受けながら、具体的な信託契約書を作成します。
この段階では、「受託者の権限」「利益の配分方法」「信託の終了時期や後継受託者の指定」などを細かく詰めていきます。
特に、複数の共有者が関係する場合は、関係者全員の合意形成を慎重に進める必要があります。
手順③:必要書類を揃えて記入する
契約内容が固まったら、正式な契約書を作成し、関係者全員の署名・押印を行います。
さらに、不動産を信託財産とする場合は、不動産登記簿に「信託の登記」を行う必要があるため、登記に必要な資料や書類を整えましょう。
登記の名義は受託者に変更されますが、所有権ではなく信託に基づく管理名義となる点がポイントです。
手順④:法務局へ登記申請を行う
必要書類が揃ったら、法務局へ登記申請を行い、信託の内容を登記簿に記載してもらいます。登記が完了した時点で、正式に家族信託が開始され、受託者による不動産管理がスタートします。
その後は、信託契約に基づいて定期的な報告や管理行為が行われ、必要に応じて内容の見直しや契約の終了手続きも視野に入れることになります。
共有持分の家族信託の締結で発生し得る費用
家族信託を利用して共有持分の管理体制を整える場合、契約の締結にあたり一定の費用が発生することがあります。実際に必要となる費用はケースによって異なりますが、以下に主な項目を挙げて解説します。
公正証書の作成費用
信託契約は紙に書かずに口頭で交わすことも理論上は可能です。しかし、実際にはトラブル防止のために公正証書での契約締結が一般的です。信託の内容を公証人が確認・認証することで、法的な証明力を持つ書面になります。
費用は、信託する財産の評価額に応じて変動します。たとえば2,000万円の不動産を信託する場合、公証役場の手数料はおおむね2〜3万円程度が相場です。また、正本・謄本の交付手数料や印紙代などが加算される場合もあります。
「契約書は自分で作れば無料」と思いがちですが、後のトラブルを避けるためには、一定の費用をかけて信頼性のある形で残すことが重要です。
登録免許税
家族信託を締結して不動産の名義を受託者へ移す場合、所有権移転登記が必要になり、登録免許税が発生します。これは国に納める税金で、税率は不動産の固定資産評価額に対して0.4%が基本です。
(参考:国税庁「登録免許税の税額表」)
たとえば、不動産の評価額が1,000万円であれば、登録免許税は4万円という計算になります。
ただし、家族信託でも「不動産の名義を変更しない」契約形態を取るケースでは、この税金は発生しません。契約内容と登記方針によって発生有無が分かれるため、事前に司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。
関連記事:共有持分移転登記費用はいくらかかる?登記の際の注意点についても解説
司法書士の報酬
登記手続きを司法書士に依頼する場合、手続き1件につき5〜10万円前後の報酬がかかるのが一般的です。登記申請自体は本人でも行えますが、必要書類の整備や申請ミスによるトラブルを避けるため、実務上は専門家に任せるケースが大半です。
また、家族信託では単なる所有権移転登記だけでなく、信託登記という特殊な形式が求められるため、一般的な登記よりも手間や確認項目が多くなります。したがって、報酬額も若干高めになる傾向があります。
「登記のどこまでを任せるか」「契約書作成も含めるか」によって費用が変動するため、見積もりの段階で業務範囲を明確にしておくことが大切です。
その他の専門家への報酬
家族信託の内容によっては、弁護士・税理士・行政書士といった専門家の関与が必要になることもあります。たとえば、次のような場面です。
- 二次相続や遺留分対策を含む契約設計
- 不動産評価や相続税の試算
- 家族間の利害調整を含めたアドバイス
報酬の相場は依頼内容によって大きく異なりますが、簡易な相談であれば1〜2万円、信託契約の設計支援まで含めると10万円以上になるケースもあります。
「どこまでを自分で行い、どこからを専門家に任せるか」によって費用は変動します。無駄な出費を避けるためにも、必要に応じて段階的に相談する姿勢が現実的です。
必要書類の取得費(※登記や契約書作成に必要な場合)
家族信託を締結する際には、登記や公正証書の作成に必要な各種書類の取得費用も発生します。たとえば以下のようなものがあります。
- 登記簿謄本(登記事項証明書):1通600円程度
- 不動産の評価証明書:1通300円〜400円程度
- 印鑑登録証明書:1通300円程度
- 住民票や戸籍謄本:1通300〜450円程度
これらは、自治体や法務局で発行するたびに手数料がかかるため、複数人の共有者が関与する信託では、合計数千円〜1万円程度の実費が発生することもあります。
少額ではありますが、信託契約書の作成や登記申請の場面で必要不可欠な費用ですので、あらかじめ準備しておくと手続きがスムーズに進みます。
家族信託以外の共有持分のトラブル解決方法との比較
共有不動産の管理や将来のトラブル回避には、家族信託のほかにも複数の選択肢があります。たとえば、「相続を明確にする遺言」「認知症に備える成年後見制度」「共有関係を法的に解消する共有物分割請求」などです。
どの手段が適しているかは、共有者の年齢や家族関係、不動産の用途、将来の見通しによって変わります。以下に、代表的な選択肢を簡潔に比較した表を掲載します。
| 方法 | 主な目的・効果 | 適しているケース |
| 家族信託 | 管理・処分の権限を受託者に集中させる | 認知症や相続トラブルを見越して計画的に管理したい場合 |
| 遺言 | 死後の財産分配に関する意思を明確にする | 相続人間の争いを防ぎたい場合 |
| 成年後見制度 | 判断能力が失われた人の財産を公的に管理 | 認知症などにより判断力が低下した場合 |
| 共有物分割請求 | 共有状態を法的に解消する | 話し合いが難航し、早期に持分関係を解消したい場合 |
なお、状況に応じてこれらの制度を併用することも可能です。
たとえば、「家族信託」と「遺言」を組み合わせることで、信託に含めなかった財産の相続先も明確にできるため、より抜け漏れのない資産管理・承継が実現できます。
関連記事:共有持分を遺言書で相続させることは可能?効力や手続きの流れを詳しく紹介
関連記事:共有物分割請求とは?請求方法や流れを解説
家族信託後の共有不動産も「ワケガイ」ならご相談可能です

当社(株式会社ネクスウィル)は、訳あり不動産に特化した買取サービス「ワケガイ」を提供しています。
家族信託を活用したものの、相続後の売却に支障が出ているケースや、共有状態が続いたままの不動産の整理にお困りの方からも、日々多くのご相談をいただいています。
特に、受託者の交代や信託契約の終了後に名義整理が滞り、不動産の流動化が難しくなる例も少なくありません。
ワケガイでは、そうした法的・実務的なハードルを踏まえた上での柔軟な買取提案が可能です。
まずは状況のヒアリングと査定から対応いたしますので、お気軽に無料査定をお気軽に無料査定をご活用ください。
まとめ
共有持分の家族信託は、将来にわたって安定した不動産管理体制を築くための有効な選択肢です。とりわけ、意思決定の停滞や認知症リスク、持分の分散といった課題を早期に解消できる点で、他の制度にはない柔軟性を持っているといえます。
ただし、契約内容を曖昧なまま進めてしまうと、かえって新たなトラブルの火種となりかねません。費用や手間がかかる場面もありますが、それを補って余りあるメリットが得られる制度でもあります。
そのため、信頼できる家族や専門家と連携しながら、「誰が、いつ、どのように管理し、最終的に誰に引き継ぐのか」を見据えた信託設計を行いましょう。