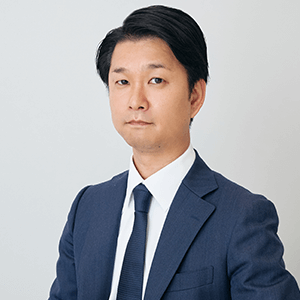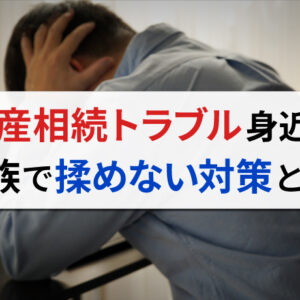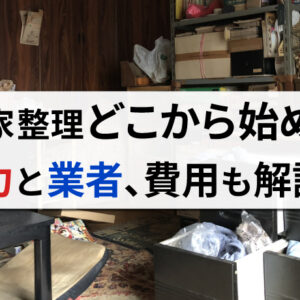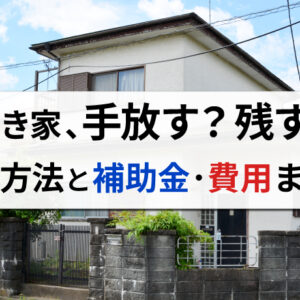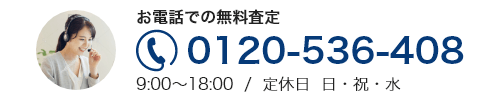について今すぐご相談できます。
お電話する
再建築不可物件を購入する際、多くのリスク要因や考慮点が存在します。不動産売買や遺産相続などで再建築不可物件を取得された方の中には、「もしかしたら何かしらのトラブルに発展するかもしれない」と不安に感じられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方のために、本稿では再建築不可物件を所有した際に発生しがちなトラブル例について解説します。適切な情報収集と対策を行うことで、これらのリスクを最小限に抑えられますので、ぜひお役立てください。
目次
再建築不可物件とは
再建築不可物件とは、その名の通り、一度取り壊してしまった場合に同じ規模や構造での再建築が許可されない物件を指します。再建築不可物件となる背景や理由は主に以下のようなものが考えられます。
- 法的制約:法律や条例の変更により、現行の建築基準に合わない。容積率、建ぺい率、高さ制限などが原因。
- 路線価の変更:公共事業(例:道路拡張)のため、土地が取られる。再建築時に土地面積が不足。
- 既存不適格:以前の法律で建築され、新しい法律では非合法となる。新しい建築では新法律が適用、再建築ができない。
再建築不可物件の特徴として、価格が安くなることが一般的。これは、将来的に建物を新しくしたり、増築したりすることができないというリスクが価格に反映されるためです。購入や投資を検討する際には、この点を十分に考慮する必要があります。
関連記事:再建築不可物件の調べ方とは?必要書類や再建築できない場合の対応方法を解説
再建築不可物件で起こりがちなトラブル
再建築不可物件で起こりがちなトラブルとしては、次のようなものが考えられます。
- 隣地との境界の認識が違う
- ブロック塀や植栽などを使って境界を区切っているケースもある
以下より、個別にみていきましょう。
隣地との境界の認識が違う
再建築不可物件は多くが古い物件であるため、隣接する土地との境界が時の流れとともに不明瞭になったり、もともと明確にされていないケースがあります。このため、物件を取得した後で隣地の所有者との間で境界に関するトラブルが生じることが考えられます。
もし隣地の所有者との境界の認識に差異がある場合、速やかに「境界明示図」を確認すべきです。この図は、土地の境界に関する紛争がないことを示す公式な書類で、「筆界確認書」や「土地境界確定書」とも呼ばれます。この図書には法的な拘束力があるため、境界に関する問題が生じた場合の解決策として非常に有効です。
実は、不動産を取引する際、売主は境界を明示する義務があります。それは、現地に境界を示す杭やプレートを設置することが「物件引渡義務」として法律で定められているからです。
境界に関する問題が生じた場合、購入した物件の売主に確認をとることや、逆に隣地の過去の取引情報を調査することが役立ちます。
関連記事:筆界未定地とは?概要や売却の方法について
ブロック塀や植栽などを使って境界を区切っているケースもある
再建築不可物件では、隣地との境界を示す手段として、ブロック塀や植栽が用いられることが少なくありません。特にブロック塀の場合、もし台風や地震などで損壊すると、境界の明瞭さが失われて紛争の元となることがあります。
ブロック塀に関する所有権は、設置の費用を負担した側に帰属します。ただし、共同で設置した場合は、両者が共有する形となります。物件の所有者が代わった結果、境界表示をいつ誰が設置したのか不明瞭になってしまうと、今後の取り扱いや費用の負担に関する認識のずれが生じる恐れがあります。
植栽を境界の表示として使用する場合も注意が必要です。植栽の管理には、枝と根に異なる法的な取扱いが存在するため、予期せぬ問題が生じる可能性があります。
具体的には、民法第233条に基づき、枝は勝手に切り取ることが禁止されているのに対し、根は第三者による切り取りが可能とされています。
適切な境界を確定する際には、これらの法的規定を超えて不適切な行動をとらないよう注意が必要です。
関連記事:再建築不可物件が起こすトラブルとは?注意点もセットで解説
再建築不可物件のトラブル回避のための注意点
再建築不可物件が起こすトラブルを回避するためには、以下の点に注意する必要があります。
- 瑕疵担保免責や契約不適合免責を確認する
- 境界を確定させる
- 未接道状態の解消や通行権の確保を請求する
それぞれについて、詳しく解説します。
瑕疵担保免責や契約不適合免責を確認する
瑕疵担保責任や契約不適合責任の免責条項は、売主と買主の間の合意に基づいて設定されます。そのため、必ずしも免責条項が設けられるわけではありません。
交渉によっては、免責条項を設けずに契約することも選択肢の1つとなります。免責条項が存在しなければ、必要に応じて瑕疵担保責任や契約不適合責任の請求が行えます。
しかし、これらの請求は煩雑でコストもかかるため、できるだけ問題が起きないよう事前の物件確認は重要です。もし問題が生じた場合は、不動産に精通した弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。
境界を確定させる
再建築不可物件の購入を考える際、最初に行うべきは売主に土地の境界の確定を求めることです。
土地の購入後に境界確定の取り組みを開始すると、土地の過去の取引や背景を正確に把握するのが難しく、隣地所有者との交渉において不利な状況に立たされる可能性が高まります。
さらに、隣接する敷地への越境や、不法占拠のリスクも考慮する必要があります。これらのトラブルを避け、安心して物件取引を進めるためにも、契約の前段階で境界の確定を要請しましょう。
未接道状態の解消や通行権の確保を請求する
未接道の課題解消や通行権の確保は、購入の前に整理してもらいましょう。
未接道の問題を解消するためには、道路との間にセットバックを設けるか、隣接する土地を買い取るなどの対策が考えられますが、それには一定のコストや隣地との協議が不可欠です。これらの課題を購入後に自ら解決するのは、手間も費用も大きくなり得ます。
売主が通行権を予め確保しておくことで、新たに物件を取得した際の利用がスムーズに進められます。ただし、日常の移動で車の利用を頻繁にしたいなど、特定の通行条件を希望する場合は、直接交渉する方が要望が伝わりやすいでしょう。
関連記事:セットバックって何?物件を再建築可能な状態にするための手順を解説
再建築不可物件が私道だった場合の注意点
購入した再建築不可物件に私道が含まれた場合、水道管・ガス管などの整備にあたって、トラブルに発展しかねない懸念材料がいくつかあります。具体的には、以下のとおり。
- 水道管が私設の可能性がある
- 水道管を整備する為の費用は自己負担になりかねない
次項より、個別にみていきましょう。
水道管が私設の可能性がある
日本国内での水道管やガス管の老朽化は近年、深刻な問題となっています。特に、水道管が私設の場合、これが老朽化や水漏れの問題を引き起こしても、独自に修繕するのは難しい状況になります。
再建築不可物件が私道に接している際、水道管の修繕に関する事前の合意や取り決めが存在しない場合、意図しないトラブルが発生する恐れがあります。
特に、相続により私道が多数の共有者を持ち、権利関係が複雑化している場合、修繕作業の際には、名義人全員の合意を得ることが不可欠です。
水道管を整備する為の費用は自己負担になりかねない
公道上に位置する水道管等のインフラの整備は、地方自治体が管理し、その費用は自治体の予算から供給されるのが一般的です。しかし、私道にある私設の水道管の整備に関する費用は、基本的に自己負担となります。
私道内の埋設物の修繕や維持に必要な費用は、所有者の負担が主流です。その際、売買契約書に「私道負担」との記載がされるケースが多々あります。
この内容は、再建築不可物件の契約時の重要事項説明の中の「私道に関する負担事項」に該当し、宅地建物取引業法第35条で法的に規定されています。
袋地である場合の通行権について
袋地は、その特性上、他の土地に完全に囲まれ、公道に直接接していない土地のことを指します。この袋地を取り囲む土地は「囲繞地」と呼ばれます。
再建築不可物件が袋地に位置する場合、公道へのアクセスには囲繞地を通ることが必要です。この際、袋地の所有者は「囲繞地通行権」を持ち、これは民法第210条に基づいて保障されています。
関連記事:袋地の不動産は再建築できない? 袋地のデメリットと対処法を解説
囲繞地や袋地の通行権と通行料について確認
囲繞地を経由する際に袋地所有者が持つ通行権には、通行料の支払いが伴います。
再建築不可物件を袋地として購入を検討する際、通行権の確認だけでなく、通行料に関する情報も十分に事前調査することが必須です。
民法により「最低限の通行」が保証されていますが、これは基本的に歩行者が通れる幅を指します。例えば、購入後の袋地から車を用いて公道へのアクセスを希望する場合、囲繞地の所有者との合意を取る必要があります。
この合意は口頭での確認も可能ですが、未来のトラブルを避けるためには、「通行地役権」を正式に設定することを推奨します。この地役権は通行を目的とした権利として登記され、囲繞地の所有者が変わってもその通行権が継続される点が特徴です。
関連記事:囲繞地(いにょうち)の通行料はいくらに設定するべき?
トラブル回避のために物件調査を専門家へ依頼しよう
再建築不可物件の購入を検討する際、独自の調査だけでは隣接する土地所有者とのトラブルや未発見の物件の欠陥などのリスクが残ります。専門家の的確な調査を受けることで、契約後の予期せぬトラブルを大きく減少させられます。
特にリスクが高い再建築不可物件においては、家屋調査士や既存住宅状況調査技術者などの専門家に物件調査を依頼することが賢明です。加えて、物件の隣地との境界が明確でない場合、確定測量の実施も考慮しましょう。
まとめ
再建築不可物件の購入は、数多くのメリットがありますが、同時にリスクも伴います。特に、袋地や囲繞地に関連する通行権や通行料、物件の詳細調査は、事前にきちんと確認しておくべき重要なポイントです。
購入希望の場合も、事前の調査と準備に時間をかけ、契約前のリスクをしっかりと理解し、対策を講じることが求められます。
再建築不可物件を取得した後に余計なトラブルに巻き込まれないようにも、事前調査では専門家の手を借りるのが賢明です。
本ブログで情報発信を行っている「ワケガイ」は、訳あり物件を積極的に買い取っている専門業者です。所有物件についてお悩みの方は、訳あり物件の買取に特化したワケガイに、ぜひお問い合わせください。
| 運営団体 株式会社ネクスウィル 2019年1月29日設立。訳あり不動産の買取を行う不動産会社。相続やペアローンによる共有持分、空き家、再建築不可物件、借地、底地など、権利関係が複雑な不動産を買い取り、法的知識や専門知識を以って、再度市場に流通させている。 |