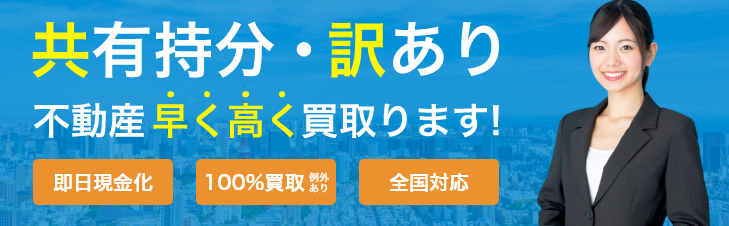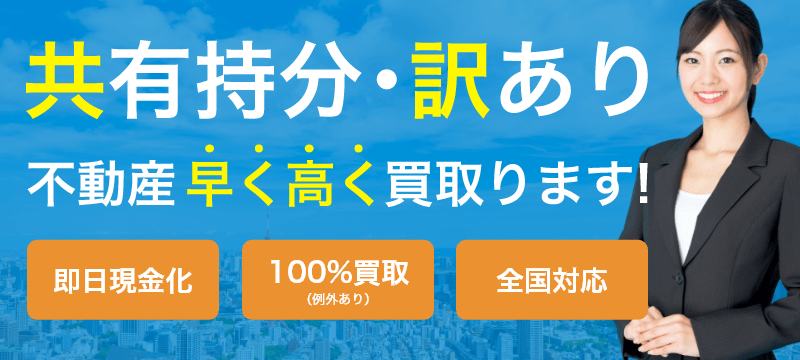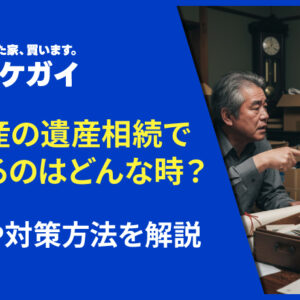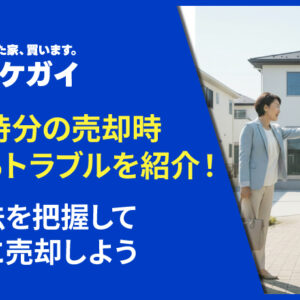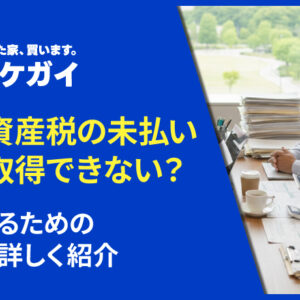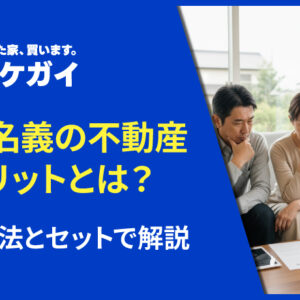親の不動産を兄弟で相続する場合、「誰が相続するか」すんなり決まらず、やむなく共有名義にするケースも少なくありません。
しかしそのまま共有状態が続くと、「売却や賃貸で意見が割れる」「管理や費用の負担が偏る」といった問題が、将来的に深刻化するリスクがあります。
その際に検討すべきなのが、兄弟での不動産共有においてトラブルを回避するための事前対策です。
そこで本記事では、「兄弟で不動産を共有すること」の基本構造と具体的なリスク、さらに将来的なトラブルを防ぐために採るべき対策について詳しく解説します。
目次
兄弟で「不動産を共有する」とはどういう状況?
「不動産の共有」は、名義となっている人全員に所有権がある一方、お互いの権利を制限している状態となります。共有名義にする際には、それぞれの共有持分を決めなければなりません。
共有持分とは、1つの不動産を2人以上で所有している際に、それぞれが持っている所有権の割合のこと。
たとえば、兄と弟で不動産を共有する際、兄の共有持分が1/2、弟が1/2だとしたら、半分ずつの権利を持つことになります。この「持分が1/2」とは、「建物の西側が兄のもの、東側が弟のもの」という物理的な考えではありません。あくまでも概念的なことになります。
兄弟で不動産を共有するケース
兄弟で不動産を共有するケースとして、代表的なものとしては「親名義の不動産を兄弟で相続する」というパターンが挙げられます。
この際、遺言や遺産分割協議により、相続人を1人に決めると単有になりますが、兄弟2人以上で相続登記をすると共有状態に陥ります。
なお、協議中で相続登記が済んでいない間は「潜在的共有状態」となり、法定相続人全員が共有しているものとみなされます。
別のケースでは「兄弟で一緒に住む家を購入する」という可能性もあるのではないでしょうか。
夫婦で暮らす住宅購入とは異なり、ペアローンが組みにくい可能性がありますが「現金での購入」「一人が現金で頭金を支払い、もう一人がローンを組む」という方法を採れば、不可能ではありません。
関連記事:実家を共有名義で相続するとトラブルになる?共有不動産の持つリスクについて論考
兄弟で不動産を共有するリスク
以上のようなケースでは、兄弟で特定の不動産を共有する可能性があります。しかし、不動産を兄弟がそれぞれ共有持分として所有することには、多くのリスクが存在します。
具体的には、次のとおりです。
- リスク①:独断で売却できない
- リスク②:賃貸運用で意思決定や責任分担が困難になる
- リスク③:管理負担の偏りで不公平感が生まれやすい
- リスク④:兄弟が住み続けても立ち退きを求められない
- リスク⑤:相続で知らない人と共有になる恐れがある
以下より、それぞれについてみていきましょう。
リスク①:独断で売却できない
不動産すべてを売却するためには、共有者全員の合意が必要になります。そのため、兄が「売りたい」と思ったとしても、弟が「売りたくない」と反対すれば、売却することができないのです。
売却だけでなく、改築や大規模な修繕など、不動産の形を変える「変更行為」や抵当権設定である「処分行為」には共有者全員の合意が必要。
銀行から資金を借りる際に「持っている不動産を担保にしたい」と思ったとしても、独断で行うことはできない点は、あらかじめ把握しておきましょう。
親族間で共有不動産を売買する方法については、以下の記事でも解説しています。こちらもあわせてご参照ください。
リスク②:賃貸運用で意思決定や責任分担が困難になる
投資用物件として兄弟で不動産を共有している場合、借主との契約内容やその変更には、共有者全員の同意が必要です。たとえ実際の運営・管理を兄が担っていても、弟が名義上の共有者である限り、弟の同意なしに契約を変更することはできません。
さらに、賃料や経費の分配に関しても、運用責任の所在があいまいになりがちです。
「赤字が出たときに誰が補填するのか」「借主とのトラブルに誰が対応するのか」といった問題が起きた場合、共有者同士で責任を押し付け合い、関係が悪化することもあります。
このように、共有名義のままでは、収益物件としての柔軟な運用やトラブル対応が極めて難しくなる点に注意が必要です。
関連記事:共有持分の「賃貸活用」は可能?賃貸借契約の役割や注意点をセットで解説
リスク③:管理負担の偏りで不公平感が生まれやすい
兄弟で不動産を共有していると、管理や費用負担のバランスが崩れやすくなります。たとえば、近隣に住む兄が草刈りや修繕の手間を担い、遠方の弟が何もしていないと、不公平感が募っていきかねません。
また、固定資産税や管理費などの請求が代表者1人に届くと、いったん立て替えた費用を他の共有者から回収しなければなりません。協力的であれば問題ありませんが、支払いを渋られたり、連絡が取れなかったりすれば、金銭的にも精神的にも大きな負担になります。
こうした不均等は、共有関係そのものを悪化させる大きな要因になり得るのです。
関連記事:共有不動産の賃貸収入はどう分配する?トラブル回避のポイントを解説
リスク④:兄弟が住み続けても立ち退きを求められない
少しでも共有持分を持っていれば、「使用する権利」があります。そのため、兄と弟で共有している不動産を兄が占有し、弟が使用できない状況であったとしても、無理やり立ち退きを要求することはできないのです。
そういったケースでは「裁判によって持分に応じた金銭の請求」「悪質な場合であれば明渡請求」をすることも不可能ではありませんが、精神的にも多大な負担増になってしまうでしょう。
関連記事:共有不動産を単独使用された場合「明け渡し請求」は可能?
リスク⑤:相続で知らない人と共有になる恐れがある
兄弟で共有名義にしていて、問題がなかったとしても、自分や兄弟の死亡で相続が発生した際には自分の子供や兄弟の子供に負担をかけてしまうリスクがあります。
なぜなら、相続を重ねるごとに共有者が増えていき、まったく知らない人同士で1つの不動産を所有しているという状態になることも考えられるため。そうなると、不動産を扱いづらくなるだけでなく、共有者同士で揉め事が起こる可能性も考えられます。
兄弟間の共有状態となりそうな際の「相続前」の3つの対応策
すでに「兄弟で不動産を共有するケース」をご紹介しましたが、誰にでも起こり得る「親からの相続」を回避するためにはどうしたらいいでしょうか。具体的な方法については、以下のようなものが考えられます。
- ①:遺産分割協議を行う
- ②:相続放棄をする
- ③:相続前に遺言書を作成してもらう
次項より、それぞれ個別に解説します。
①:遺産分割協議を行う
遺産分割協議とは、相続が発生したときに相続人全員で遺産の分け方について話し合うことです。話し合いで取り決める内容は、「不動産を相続する人は誰にするか」「不動産自体を手放すか」など。
遺産分割協議での決定には「相続人全員が同意した」という証拠が必要であり、相続人全員の実印が押された「遺産分割協議書」と、全員分の印鑑証明書が必要となります。つまり、誰か1人でも反対の状態であれば成立することができないのです。
不動産の分割方法は3パターンあるため、個別に紹介します。
現物分割
相続した財産の形や性質を変えることなく、そのまま各相続人に分配する方法です。
たとえば「兄には不動産、弟には預貯金という形で分割する」「土地を分筆して自分の持分を相手に譲る(交換)」などの方法で、それぞれ単有の土地に変えられます。
関連記事:現物分割とは?メリット・デメリットや検討すべきケースを解説
価格賠償
相続人を1人選び、その人が相続した代償として、他の兄弟に金銭を支払う方法です。相続した財産が不動産しかない場合に行うことが多い手法です。
遺産分割協議書に「代償分割により財産を支払う」という旨を記載しないと、贈与税がかかる可能性がある点には留意しましょう。
関連記事:「代償分割」とは?共有持分の分割方法方法として選ぶべきケースを解説
換価分割
不動産を含む財産のすべてをお金に変えて、各相続人に金銭で分配する方法です。
不動産を売却するためには故人名義では売れないため、相続登記が必要。この際、相続人2人以上の名義で登記をすると共有状態となり、売却時に共有者全員の合意や立ち会いが必要となるため、代表者1人を選ぶようにしましょう。
なお、「換価分割のための相続」であることを対外的(役所など)にわかるようにしておかなければ、贈与税課税を求められてしまうリスクがあります。課税を回避するためにも、遺産分割協議書に「換価分割をするため」と、記載しておきましょう。
関連記事:共有持分の「換価分割」とは?メリット・デメリット、選択すべきケースを紹介
②:相続放棄をする
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産または負債を承継せず、相続人である地位を放棄することです。
相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになるため、遺産分割協議に参加できず、相続する予定であった財産などは他の相続人で分配することになります。
つまり、不動産の共有状態を避けることはできますが、他の遺産を受け取ることもできなくなるということ。
相続放棄をするためには「放棄します」と発言するだけでは成立せず、家庭裁判所に申述する必要があります。期間も定められており、被相続人の死亡を知ったときから「3ヶ月以内」が原則です。
③:相続前に遺言書を作成してもらう
兄弟間で協議することが難しいと想定される場合、相続が発生する前に親などに遺言書を作成しておいてもらいましょう。遺言書をもとに手続きをするためには、「有効な遺言書」が必要。
自分で書いたものは法的有効性をクリアしていない場合があるため、公証人が内容を確認して、公証役場に保管をする「公正証書遺言」を選択するのが賢明です。遺言書を残しておけば、遺産分割協議が不要になる点がメリットです。
遺産分割協議や遺言書で不動産の相続人を誰にするか決まったら、必ず「所有権移転登記(相続登記)」を行いましょう。
そのままにしておくと、潜在的共有状態が解消されず、法定相続人全員が所有していることになってしまうためです。相続登記をすれば、はじめから登記人の単有不動産とみなされます。
関連記事:共有持分を遺言書で相続させることは可能?効力や手続きの流れを詳しく紹介
すでに兄弟で不動産を共有している場合の解消法
すでに兄弟で不動産を共有している場合、どのようにしたら解消できるのでしょうか?ご紹介します。
- 売却
- 分筆(※土地の場合)
- 交換(※不動産が複数ある場合)
- 贈与
- 相手方の持分の買取
- 共有物分割訴訟
以下より、それぞれについてみていきましょう。
売却
不動産の共有状態を解消する方法として、最も現実的かつ迅速なのが「売却」です。
兄弟で共有している場合、「共有者全員で不動産を売却する方法」「自分の持分だけを手放す方法」の2通りがあります。
売却の選択肢①:すべての持分を兄弟全員で売却
不動産全体を売却して売却益を兄弟で分配すれば、共有関係をスムーズに解消できます。市場価格に近い金額で売却できるため、経済的なメリットも大きいのが特徴です。
ただし、売却には共有者全員の同意と協力が不可欠です。登記上の手続きに加え、印鑑証明書の提出や買主との面談などが求められる場合もあります。
兄弟間で足並みが揃わないと成立しにくい方法ですが、話し合いが可能な場合には非常に有効です。
関連記事:共有持分の不動産を売却する方法とは?売却費用やよくあるトラブルを紹介!
売却の選択肢②:専門業者に自分の持分のみを売却
他の兄弟の同意が得られない、もしくは将来的なトラブルを回避したい場合には、「持分だけを専門業者に売却する」という方法もあります。
一般の個人にはなかなか売れない共有持分でも、訳あり不動産を専門とする業者であれば、買い取ってもらえる可能性があります。
早期に共有状態から抜け出したい人にとっては、有効な手段です。買取価格は単独での不動産売却に比べると低くなりがちですが、将来の煩雑なトラブルや相続リスクを避けられるという意味では、十分に検討の価値がある選択肢でしょう。
関連記事:【2025年版】共有持分の買取業者のおすすめ厳選5社!今買取をお願いするべき専門業者とは?
分筆(※土地の場合)
分筆とは、ひとつの土地を物理的に分け、それぞれを別の登記簿として管理できるようにする手続きです。共有状態にある不動産が「土地」の場合、この分筆によって個別所有へと移行する道が開かれます。
たとえば、兄と弟で1筆の土地を共有している場合、境界を定めてそれぞれの単独所有に切り替えることが可能です。
ただし、分筆後もお互いの持分が混在している状態では単有にはなりません。あらためて持分を譲渡し合うなどの登記手続きを経て、完全な単有化を目指す必要があります。
分筆には測量や隣地との境界確定、土地家屋調査士の関与などが必要になるため、早めの準備が大切です。
関連記事:共有持分通りに土地を分筆する方法とは?手順について詳しく解説!
交換(※不動産が複数ある場合)
交換とは、兄弟で複数の不動産を共有している場合に、それぞれの不動産の所有権を譲渡し合って単有にする方法です。たとえば、「A物件は兄に、B物件は弟に」といった形で共有を解消できます。
この方法の利点は、不動産の数が2つ以上ある場合に、それぞれの持分に応じて分け合える点にあります。さらに、「固定資産の交換の特例」を活用すれば、一定条件を満たすことで譲渡所得税の課税を繰り延べにできる可能性もあります。
ただし、特例を受けるためには面積や用途などの要件を満たす必要があり、税務署への確認も重要です。
関連記事:共有持分の「交換」とは?共有関係を解消する方法を詳しく解説
贈与
兄弟間で「共有持分を譲りたいor譲ってもよい」という合意がある場合、贈与によって単有に切り替える方法もあります。たとえば、弟が兄に持分を無償で譲るような場合が該当します。
ただし、贈与は税制上の負担が大きくなりやすい点に注意が必要です。
贈与税は、もらった不動産の評価額に基づいて課税され、110万円を超えると基礎控除を超過した分に対して課税されます。特に共有持分の贈与であっても例外ではなく、場合によっては数十万円〜数百万円の税負担が発生する可能性もあります。
(参考:国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」)
関連記事:親子共有名義の不動産は生前贈与するべき?注意点について徹底解説!
相手方の持分の買取
兄弟のどちらかに資金的な余裕があれば、他方の持分を買い取って単独名義にすることで、共有状態を解消できます。反対に、自分が不動産を手放したい場合は、相手に売却することも可能です。
価格は不動産全体の評価額をもとに持分割合で決めるのが基本ですが、実際には双方の合意が前提です。税務面では譲渡所得税が発生する可能性もあるため、事前に確認しておくと安心です。
関連記事:共有持分の買取請求とは?具体的な方法やメリット、デメリットを解説
共有物分割訴訟
もし、兄弟間で話し合いができない状態である。あるいは自分たちでは解決に導くことができない場合、共有物分割請求を検討しましょう。
調停によって解決しなければ、裁判所が客観的に分割の方法(現物分割、価格賠償、換価分割)やその内容などを取り決めることが可能です。
関連記事:共有物分割請求とは?請求方法や流れを解説
「兄弟で共有している不動産」もワケガイなら買取可能!

当社(株式会社ネクスウィル)は、共有持分や複雑な権利関係を抱える不動産の買取に特化したサービス「ワケガイ」を提供しています。
兄弟間で共有している不動産は、売却や活用の際に全員の同意が必要となり、思わぬ足止めや対立を招くことがあります。さらに、相続を重ねることで関係者が増え、手続きがますます困難になるケースも少なくありません。
ワケガイでは、共有状態のままでも売却できる体制を整えており、共有者の方おひとりでのご相談でも対応可能です。経験豊富なスタッフと士業チームが、現地調査から法的調整まで丁寧にサポートいたしますので、お気軽に無料査定をご活用ください。
まとめ
不動産を兄弟で共有することは、感情的な対立を避けた“その場しのぎ”として選ばれることが少なくありません。
しかし専門家の視点から見ると、共有状態を長く維持すること自体が、将来的なトラブルの種を抱える行為でもあります。
意思決定が複雑になり、費用や管理責任が曖昧になれば、かえって関係が悪化するリスクが高まります。
実務上、「今は揉めていないから大丈夫」と考える人ほど、後に困難な事態に直面する傾向があります。
相続や共有は“起きてから考える”では遅く、冷静にシミュレーションしたうえで、可能な限り単独所有に切り替えるための手段(分筆・贈与・売却・買取など)を早い段階から検討しましょう。
関連サイト:兄弟で借地権を相続する場合は遺産分割がおすすめ!共有するデメリットや相続の注意点を紹介 – 借地権無料相談ドットコム