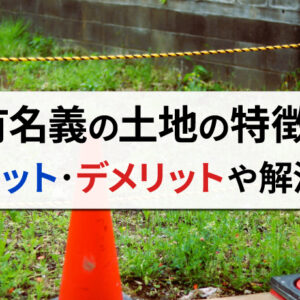こんにちは。ワケガイ編集部です。
共有名義の不動産をめぐって、「思うように売却できない」「修繕費の分担で話がまとまらない」「共有者が増えすぎて管理できない」といった悩みを抱える方は少なくありません。
特に相続によって「共有持分」が発生した場合、当初は問題なく見えた関係性が、時間の経過とともに行き違いや責任の曖昧さを生み、やがて不動産の放置や争いにつながることもあります。
共有持分には、他の共有者との合意が前提となる性質があり、それが思い通りに活用できない最大の原因となりがちです。
本記事では、共有持分の基本的な仕組みから、メリット・デメリット、現実的な解消方法までわかりやすく解説します。
目次
共有持分とは
共有持分とは、1つの不動産を複数人で所有している場合における、各人が持つ所有権の割合を指します。たとえば、実家を兄弟3人で相続し、分けずに共同で所有することになった場合、それぞれが「3分の1ずつの共有持分」を持つことになります。
民法ではこの状態を「共有」と呼び、第250条において以下のように定められています。
“各共有者は、その持分に応じて、共有物の負担に任ずる”
引用:民法第250条
つまり、共有持分は単に所有割合を示すだけでなく、利用権・費用負担の基準としても機能するということです。
なお、不動産を相続によって発生することが多く、持分割合は遺言や遺産分割協議によって決まります。遺産分割が未了の状態では、法定相続分に基づく共有状態となるのが一般的です。もちろん、話し合いによって1人が単独で相続し、共有を避けることも可能です。
関連記事:共有持分を相続しなければならない可能性がある場合、相続放棄は可能?
関連記事:実家を共有名義で相続するとトラブルになる?共有不動産の持つリスクについて論考
共有持分権とは
共有持分権とは、財産を複数の人で共有している際、その共有持分やそれに伴って発生するさまざまな権利のことを指します。
共有持分権者は、持分に応じて権利を持っているものの、「持分が半分だから建物の半分が自分のもの」という具体的な内容ではなく、「不動産全体に対し半分の割合の権利を持っている」という抽象的な考えです。
共有持分はなぜ発生する?
不動産を共有するのは、以下のようなケースが考えられます。
<共有持分が発生するケース>
| ケース分類 | 内容の概要 |
| 共同購入 | 夫婦・親子・兄弟・友人などが資金を出し合って不動産を購入するケース。住宅ローンを分担する場合も含まれる。 |
| 相続 | 複数の相続人が同じ不動産を相続し、持分を分けないまま共有状態になるケース。遺産分割協議が整わない場合もある。 |
| 贈与 | 不動産を複数人に分けて贈与するケース。例:親が子どもたちに均等に持分を贈与するなど。 |
| 投資目的の共有 | 賃貸物件などの収益目的で複数人が出資し、共同で不動産を保有するケース。法人化せずに行うこともある。 |
| 事業・法人の共有財産 | 複数の事業者や法人が業務用地などを共同で所有しているケース。登記上も法人や複数の名義人が記載されている。 |
| 財産分与 | 離婚時に夫婦間で不動産を完全に分割せず、それぞれが持分を保有する形で分与されるケース。 |
特に、夫婦でマイホームを共同購入するケースや、相続によってアパートなどの賃貸物件を兄弟で引き継ぐケースは一般的です。しかし、これら以外にもさまざまな状況で共有持分が発生することがあり、それぞれに特徴やリスクが伴います。
【自由度順】共有持分で認められる行為・権利
共有持分を持っているからといって、常に自由に不動産を活用できるとは限りません。実際には、行使できる範囲に差があり、他の共有者の同意が必要になるケースも多くあります。
そこで本章では、共有不動産に対して可能な行為を「自由度の高い順」に整理し、それぞれどこまで単独で行えるのか、どのような合意が求められるのかを明確にしていきます。ご自身の判断材料として役立ててください。
保存行為(単独で実行可能)
保存行為とは、共有不動産の状態を維持し、価値の低下を防ぐための行為を指します。他の共有者に不利益を与えない限り、こうした行為は共有者が単独で実施できます。修繕や不法占拠者の排除など、物件を守る目的の行動が主な対象です。
とはいえ、自由に行えるからといって、事後の説明や配慮を欠くと共有者間の関係悪化を招くこともあります。一例を挙げると、自費で修繕を行ったあとに費用の分担を求める場合、他の共有者にとっては「知らされていなかったのに請求された」という印象を持たれるおそれがあります。
こうしたトラブルを避けるためには、事前または事後に通知を行いつつ、写真や見積書・領収書などの記録を残しておくことが有効です。実務では、正当性の証明が後から求められる場面も多いため、慎重な対応が望まれます。
<保存行為の例>
- 建物の軽微な修繕(屋根の雨漏り、外壁の補修など)
- 無断占拠者に対する明渡し請求
- 相続に伴う所有権移転登記
- 登記名義の誤り訂正や抹消請求
使用行為(共有物全体の利用は可能、ただし制限あり)
共有者は、自身の持分に応じて、共有物全体を使用する権利を持っています。たとえば、共有名義の実家を一時的に使ったり、庭を利用したりすることは、当然の権利として認められています。
ただし注意が必要なのは、これは「物件全体に対する共有的な利用」であって、「自分の持分に相当する部分だけを自由に専有してよい」という意味ではないという点です。共有者の1人が黙って居住を始めたり、単独で物件を貸し出したりすれば、他の共有者にとって不公平と感じられる可能性が高くなります。
共有物の使用については、形式上自由であっても、他の共有者と事前に話し合い、合意を得ておくことが現実的な解決策といえるでしょう。
<使用行為の例>
- 実家の一部を居住スペースとして利用する
- 共有スペース(庭・納屋など)の使用
- 利用区分を話し合いで決めたうえでの専用利用
- 「黙示の専有状態」と見なされた場合には、法的問題に発展することもある
関連記事:共有持分の使用貸借は解消できる?共有時のトラブルを回避する方法とは
管理行為(持分の過半数による合意が必要)
管理行為とは、物件の利用や収益化など、日常的な運用に関わる意思決定を指します。共有者のうち、持分の合計が過半数に達する同意があれば実行可能とされており、全員一致は不要です。
たとえば、空き家となった実家を第三者に賃貸する、駐車場の使い方を取り決める、といった行為が該当します。
注意したいのは、ここでいう「過半数」が人数の多数決ではなく、持分割合に基づく点です。たとえば3人で共有していても、Aが2分の1、BとCがそれぞれ4分の1ずつ持っている場合、Aの単独同意で管理行為が成立する可能性があります。
なお、共有物件に火災保険をかける場合は、共有者のうち1人を「代表者」として契約者に指定するのが一般的です。保険会社は共有者全員との契約を前提とはしておらず、代表者名義での契約となります。
保険料の支払いや保険金の受け取りに関しても、事前に共有者間で方針をすり合わせておくと、不要な衝突を防ぐことができるでしょう。
<管理行為の例>
- 空き家を第三者に賃貸する契約を締結する
- 賃貸借契約の更新・解約
- 修繕・管理費の分担方法を決める
- 駐車スペースや共用部分の利用ルールを整備する
- 共用エリアの用途変更や定期清掃の実施方針を決める
関連記事:共有持分の管理行為とは?できること・できないことと対処法をわかりやすく解説
関連記事:共有不動産の火災保険は誰が支払うべき?保険金の受取人は?
変更・処分行為(全員の合意が必要)
変更・処分行為とは、不動産の性質や権利関係そのものを大きく変えてしまう行為を意味します。具体的には、建物を取り壊して更地にしたり、売却したりする行為はこれに該当します。
共有者全員の同意がなければ実行できず、たった一人でも反対すれば計画は立ち行かなくなります。
こうした合意の難しさから、現実には「売りたくても売れない」「建て替えしたくても進まない」といった膠着状態に陥るケースが少なくありません。特に相続を経て共有者が増えた物件では、そもそも連絡すら取れない共有者が存在することもあります。
このような状況においては、家庭裁判所での共有物分割請求や、他の共有者への持分売却、または買取業者への売却といった別の手段を模索する必要があるでしょう。
<変更・処分行為の例>
- 不動産の売却(共有持分全体)
- 建物の取り壊し・建て替えの決定
- 分筆や合筆など登記上の構造変更
- 長期(20年以上)の賃貸借契約締結
- 抵当権・地上権などの担保権設定
共有持分のメリット
共有不動産にはリスクや制約もありますが、一方で特定の状況下では金銭的なメリットが得られることもあります。以下に、代表的な2つのメリットをご紹介します。
メリット①:住宅ローン控除を夫婦それぞれで活用できる
共有名義で住宅を購入し、夫婦がそれぞれ住宅ローンを契約している場合には、一定の条件を満たすことで、双方が、「住宅ローン控除(マイホームを売ったときの特例)」を受けられるケースがあります。
(参考:国税庁「マイホームを売ったときの特例」)
住宅ローン控除とは、年末時点の住宅ローン残高または購入価格のうち低い方の1%を、一定期間、所得税から差し引ける制度です。
ただし、双方が要件を満たしている必要があり、契約の方法や住民票の届け出方によっては適用されない場合もあります。購入時点での慎重な設計が求められますが、共有名義ならではの制度的な恩恵の一つといえるでしょう。
メリット②:高額物件でも資金を出し合って購入しやすい
不動産を単独で購入するのが難しい場合、家族や配偶者と資金を出し合って共有名義で取得するという方法があります。これは、高額な物件を視野に入れたいときや、ライフスタイルの変化に応じて柔軟な資金計画を立てたいときに、現実的な選択肢となります。
夫婦がそれぞれ1,500万円ずつ出資して3,000万円の住宅を購入するとしましょう。この場合、持分を2分の1ずつに設定することで、出資比率に応じた公平な名義設定が可能です。
親子や兄弟での共同購入であっても、登記時に持分を調整することで、将来的な相続や売却に備えた管理がしやすくなるという面もあります。
関連記事:不動産共有のメリット・デメリットとは?マイホーム購入の際の判断基準を紹介
共有持分を所有し続けるデメリット
不動産を複数人で共有すると、1人で所有する場合に比べて自由度が制限されることが多く、デメリットやリスクも多岐にわかります。具体的には、以下のものが挙げられます。
- デメリット①:利活用が難しい
- デメリット②:相続により権利関係が複雑になる
- デメリット③:他の共有者の持分が第三者に売却される恐れがある
- デメリット④:他の共有者の借金により持分が差し押さえられることがある
それぞれ個別にみていきましょう。
デメリット①:利活用が難しい
前述のとおり、共有名義の不動産は、共有者それぞれが単独で自由に使えるものではありません。一定の行為には持分の過半数、あるいは全員の合意が必要とされるため、共有者間で意見が分かれた場合には、物件の活用が思うように進まなくなることがあります。
たとえば、空き家となった実家を賃貸に出したいと考えても、他の共有者が「思い出があるから残したい」と反対すれば、それだけで話は止まってしまいます。また、修繕の必要が生じた場合でも、費用負担についての意見がまとまらず、放置されるケースも少なくありません。
特に、相続などで共有者が増えた場合は、連絡や意思決定の調整が難しくなり、結果として物件が放置され老朽化していくといった事態も現実に起こっています。
関連記事:共有持分のリスクとは? 共有状態はなぜリスクが高いのか?
関連記事:共有名義不動産を「独り占め」したらどうなる?問題発生時の解決方法について紹介
デメリット②:相続により権利関係が複雑になる
共有不動産は、相続が発生するたびに持分の所有者が増えていく傾向があります。たとえば、親と子2人の3人で所有していた不動産を、子どもがそれぞれ自分の子どもに相続すると、次の世代ではさらに所有者が増えることになります。
こうした状態が繰り返されると、最終的には誰がどれだけの権利を持っているのかが分かりにくくなってしまいます。
また、共有者が増えることで、前述の利活用の問題もさらに深刻になります。所有者全員の合意が必要な場面で話し合いが難航しやすく、結果的に「誰も管理しない」「売却もできない」といった状況に陥りかねません。
さらに、遠方に住んでいる共有者がいる場合や、相続によって持分の一部が海外に渡った場合などは、連絡を取ること自体が困難になることもあります。
デメリット③:他の共有者の持分が第三者に売却される恐れがある
共有持分は、それぞれの共有者が単独で自由に売却できる権利を持っています。つまり、他の共有者の同意がなくても、自身の持分を第三者に売ることが可能です。
この仕組みにより、突然見知らぬ第三者が新たな共有者として登場するという事態が起こり得ます。たとえば、親族が共有する実家の持分を、経済的理由から1人が不動産買取業者に売却した場合、残された共有者は赤の他人と一つの不動産を共有する状態に置かれることになります。
新たな共有者が利活用や売却を強く求めてくるケースもあり、トラブルに発展することも少なくありません。こうした事態は、**自分が注意していても防げない「外からのリスク」**である点が厄介です。
デメリット④:他の共有者の借金により持分が差し押さえられることがある
共有者の一人に多額の借金がある場合、その人の持分が債権者に差し押さえられ、競売にかけられる可能性があります。これは、債権回収の一環として、持分が財産として扱われるためです。
競売で落札された持分は、第三者(ときには投資目的の買取業者)に取得されることが多く、結果として共有状態が不安定化することになります。
たとえ自身にまったく非がなくても、他人の金銭トラブルに巻き込まれるリスクがあるという点は、共有ならではの重大な弱点といえるでしょう。
また、競売にかかった後は、落札者が共有物分割請求を行う可能性もあり、共有状態の継続が困難になることもあります。
関連記事:共有持分が差し押さえられた場合の対処法とは?強制執行の影響も踏まえて詳しく解説
関連記事:他の共有者の持分が競売にかけられた場合の対処法は?未然に防ぐ方法はある?
共有持分を所有していると発生する税金の種類
共有持分を所有していると、単独所有の不動産と同様に、税金の支払い義務が生じます。税額は通常、持分の割合に応じて計算されますが、共有ならではの煩雑さもあるため、事前に知っておくと安心です。
特に問題になりやすいのが、納税通知書が代表者のもとに届くため、共有者同士で支払いの分担がうまくいかないケースです。こうしたトラブルを避けるには、あらかじめ支払方法や連絡体制を共有者間で取り決めておくことが重要です。
以下に、共有持分を持つことで発生しうる主な税金とその概要をまとめました。
| 税金の種類 | 内容と注意点 |
| 固定資産税・都市計画税 | 毎年課される税金。持分割合に応じて負担する。納税通知書は代表者に届くのが一般的。 (参考:総務省「固定資産税」「都市計画税」) |
| 不動産取得税 | 不動産を取得した際に一度だけ課税される。持分の売買・相続・贈与の各ケースで発生する。(参考:総務省「不動産取得税」) |
| 譲渡所得税・住民税 | 共有持分を売却した場合、利益(譲渡所得)に応じて課税される。持分のみの売却でも課税対象となる。(参考:国税庁「土地や建物を売ったとき」) |
これらの税金は、不動産を所有している限り避けられないものです。共有状態が長引くと、誰がどの税金をどのように支払うのかで揉める原因にもなり得るため、共有持分を整理・解消することが、税務リスクの低減にもつながるといえるでしょう。
関連記事:共有持分にかかる税金一覧!計算方法や控除制度もセットで徹底解説
関連記事:共有名義の「固定資産税」は誰が払うべき? 滞納した場合や支払いたくない場合はどうなる?
関連記事:共有持分を取得した場合にかかる「取得税」とは?節税対策もセットで解説
不動産の共有状態を解消する方法
共有不動産は、所有者が複数いることで意思決定が難しくなったり、自由に活用できなかったりするケースが多くあります。
こうした問題を解決するためには、持分を整理し、単独所有にするか、適切な方法で処分することが重要です。共有持分を解消する主な方法としては、以下の3つが代表的です。
- 方法①:共有持分の売却
- 方法②:共有持分の分割
- 方法②:共有持分の放棄
それぞれ個別にみていきましょう。
方法①:共有持分の売却
共有持分の売却とは、所有している持分を他の共有者や第三者に売ることです。持分を売却することで、共有状態を解消することも可能です。売却には主に以下の2つの方法があり、それぞれメリット・デメリットが異なります。
①-1:一般的な不動産仲介を利用する
共有持分のみを売却する際、まず検討されるのが不動産仲介会社を通じた売却方法です。ただし、一般的な不動産市場では、「持分だけを購入したい」という買主は非常に限られています。
理由としては、持分だけを取得しても物件全体を自由に使えるわけではなく、活用に制約があるためです。そのため、仲介を通じた売却は以下のような条件に合致する場合に限定されやすくなっています。
通常の物件売却に比べて売却期間が長期化しやすく、価格交渉も不利に働く可能性があるため、時間と労力に余裕がある場合に限られるでしょう。
<一般的な不動産仲介が向いているケース>
- 他の共有者が購入に応じてくれる(=共有者間売買)
- 元から持分購入を希望している投資家が現れる
関連記事:共有持分の不動産を売却する方法とは?売却費用やよくあるトラブルを紹介!
関連記事:共有名義のマンションは売却できる?放置するリスクや売却方法を紹介
①-2:専門業者に買取を依頼する
共有持分の場合、訳あり物件に特化した不動産買取業者に相談した方がスムーズな場合も多々あります。こうした業者は、他の共有者との交渉や権利関係の調整に慣れており、持分単独での売却にも柔軟に対応してくれるのが特徴です。
「一刻も早く共有状態を解消したい」「他の共有者と連絡がつかない」など、複雑な事情を抱えている場合には、現実的かつ有力な選択肢となります。
なお、あらかじめ共有持分の売却価格の決まり方も把握しておき、買取業者から提示された査定額については、金額だけでなく査定額の「根拠」についてしっかりチェックしましょう。
専門業者による買取の主な特徴は以下のとおりです。
<専門業者への買取依頼が向いているケース>
- スピード重視(最短即日で売却完了となる場合も)
- 交渉の負担が少ない(共有者との調整を代行してくれることもある)
- 価格は仲介よりやや低めに設定されることが多い
関連記事:【2025年版】東京都の共有持分に強い買取業者6選!
方法②:共有持分の分割
共有持分の分割とは、共有者それぞれが単独所有となるように、不動産を分けることです。 共有者ごとに独立した所有権を持つことで、共有状態の問題を解消できます。
分割には3つのの種類があり、状況に応じた適切な方法を選ぶ必要があります。
②-1:現物分割
現物分割とは、不動産を物理的に分け、それぞれの共有者が単独で所有する形にする方法です。たとえば、広い土地を分筆して、それぞれの区画を個別に登記すれば、共有状態を解消できます。
この方法は、不動産自体に分割可能な余地があること、かつ共有者間で分割内容に合意が取れていることが前提となります。
ただし、建物は原則として物理的に分割できないため、現物分割が適用できるのは主に土地に限られます。また、分筆にあたっては測量や境界確定が必要になるため、費用と時間がかかる点にも注意が必要です。
地域の条例や建築基準法上の制限によっては、分筆後に建築できない「再建築不可地」になるおそれもあるため、専門家への事前相談が不可欠です。
関連記事:現物分割とは?メリット・デメリットや検討すべきケースを解説
関連記事:「共有物分割請求」と「不動産の交換」の違いとは?
②-2:代償分割
代償分割とは、不動産を一人の共有者が単独で取得し、その代わりに他の共有者へ金銭(代償金)を支払うことで持分を整理する方法です。
たとえば、兄弟で共有していた家を兄が取得し、弟に持分相当額の現金を支払うといったケースが代表的です。この方法は、現物分割のような土地の分筆が不要で、物件を維持したまま共有状態を解消できる点が大きなメリットといえます。
ただし、代償金の額について合意が取れないと交渉が長期化するおそれがあり、また、取得者側に相応の資金的余裕が必要となります。
遺産分割協議においても頻繁に用いられる方式ですが、不動産評価の方法や負担割合に関する調整が必要になるため、司法書士や税理士などの関与が推奨されます。
関連記事:「代償分割」とは?共有持分の分割方法方法として選ぶべきケースを解説
②-3:換価分割
換価分割とは、共有している不動産そのものを売却し、その売却代金を共有者間で分け合う方法です。現物分割が難しい場合や、代償分割を行うだけの資金が共有者間にない場合に選ばれる、比較的中立的で現実的な解決手段です。
この方法の大きな特徴は、共有者全員が協力して不動産全体を売却することで、共有状態そのものを終了させられるという点にあります。売却益は持分割合に応じて分配され、共有名義の関係もこれを機に解消されます。
なお、同じく「売却によって共有関係から抜ける」手段として、「共有持分の売却」がありますが、両者には重要な違いがあります。
「共有持分の売却」は、自分の持分だけを単独で第三者に売る方法であり、他の共有者の合意は不要です。その結果、共有関係は解消されず、新たな第三者が共有者として加わることになります。
これに対して換価分割は、共有者全員が合意して不動産全体を売却するため、取引後に共有関係そのものが残らないという点で、最終的な清算手段として位置づけられます。
関連記事:共有持分の「換価分割」とは?メリット・デメリット、選択すべきケースを紹介
方法②:共有持分の放棄
共有持分の放棄とは、自分の持分を手放し、他の共有者に権利を譲る行為を指します。
共有持分を放棄すると、他の共有者がその持分を引き継ぐ形になります。自らの持分を手放すことで管理の負担から解放されますが、放棄した持分は国庫に帰属せず、他の共有者のものとなるため、事前に合意を取ることが重要です。
また、持分を持つことで発生していた固定資産税の負担からは解放されますが、債務が残る場合は注意が必要です。
関連記事:共有持分は放棄できる?具体的な手順や発生する費用をチェック!
関連記事:共有名義の不動産を「名義変更」する方法とは?
共有持分にお悩みの方は「ワケガイ」にご相談ください!

当社(株式会社ネクスウィル)は、共有持分をはじめとする訳あり不動産の買取に特化した「ワケガイ」を運営しています。通常の市場では売却が難しい物件でも、豊富な実績と専門的なノウハウを活かし、迅速な対応を可能にしています。
共有持分の不動産は、所有者が複数いるため単独での売却が難しく、買い手を見つけるのに時間がかかることが少なくありません。こうした問題を抱える方に向けて、ワケガイでは単独持分の買取を行い、スムーズな売却をサポートしています。
売却を検討しているが「共有者との交渉が進まない」「売れるのか分からない」「早く手放したい」といった悩みをお持ちの方は、お気軽に無料査定をご活用ください。
まとめ
共有名義の不動産は、一見すると公平な形に見えても、実際の管理や活用の場面では多くの壁に直面します。誰か一人の意思だけでは前に進めず、気づけば長年放置されてしまうことも少なくありません。
とはいえ、共有持分の扱いには法律上のルールがあり、自分の持分であってもできることとできないことが明確に分かれています。
だからこそ、現状を正しく整理し、自分にとってどの方法が現実的なのかを冷静に判断していくことが大切です。共有状態を放置していても、時間とともに状況は複雑になりかねません。まずは、自分の持分がどのような状態にあるかを確認し、必要であれば早めに専門家へ相談するなど、着実な問題解決を図りましょう。