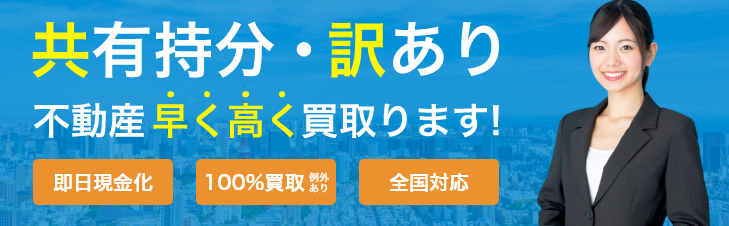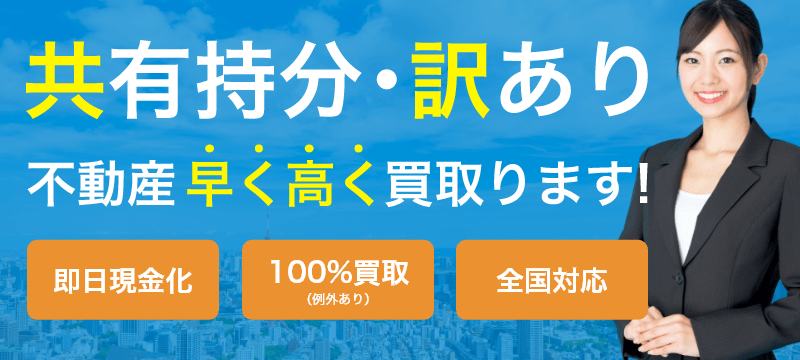こんにちは。ワケガイ編集部です。
相続や売却をめぐって共有持分の扱いを検討していると、「税金の負担がどれくらいかかるのか分からない」「どんな手続きが必要なのかイメージできない」といった悩みを抱えることが少なくありません。
共有持分は、単なる不動産とは異なり、所有しているだけでも固定資産税などの税金が発生し、取得や売却の場面でも特有の課税が行われます。
しかも、税金の種類ごとに適用される控除や軽減措置は細かく、適用条件も厳しいため、知らないと本来受けられるはずの優遇を逃してしまうリスクもあります。
そこで本記事では、共有持分に関わる主な税金の種類と基本的な仕組み、活用できる控除や軽減制度について、整理してわかりやすく解説します。
(※本記事の内容は2025年4月時点のものです)
目次
共有持分に関わる税金一覧
共有持分に関する税金は、単に所有しているだけの場合、取得した場合、売却した場合で、それぞれ異なります。状況ごとにかかる税金や利用できる控除・特例も変わるため、整理して押さえておくことが重要です。
以下に、共有持分に関わる主な税金と控除制度をまとめます。
| ケース | 発生する主な税金 |
| 共有持分を所有している場合 |
|
| 共有持分を取得した場合 |
|
| 共有持分を売却した場合 |
|
上記のとおり、共有持分にかかる税金と使える制度は、所有・取得・売却といった各フェーズで異なります。
なお、また、共有持分に関連して利用できる各種控除・軽減措置には、適用条件が厳格に定められているものも多く、すべてのケースで活用できるとは限りません。実際の利用可否については、事前に十分な確認が必要です。
共有持分を「所有」していると発生する税金
共有持分を「所有」している状態とは、特定の不動産に対して、単独ではなく他者と共同で権利を持っている状態を指します。
持分割合に応じた権利を有しつつ、他の共有者と共同で管理・利用を行うため、自由に物件を処分できないなどの制約も存在します。
共有持分を所有している場合に発生する主な税金は、以下のとおりです。
- 固定資産税
- 都市計画税
それぞれについて、どのような仕組みで課税されるのか、個別に詳しく解説していきます。
所有時に発生する税金一覧
固定資産税
固定資産税とは、土地や家屋、建物、設備などの固定資産に対して課される地方税(市町村税)です。課税対象となるのは、毎年1月1日時点の登記簿上の所有者となります。
(参考:総務省「固定資産税」)
税額は、不動産の「固定資産税評価額」に税率1.4%(標準税率)をかけて算出されます。ただし、自治体によっては財政状況などを踏まえ、1.4%を超える税率を設定しているケースもあります。
支払い方法は自治体により異なりますが、一般的には以下の手段が用意されています。
- 金融機関やコンビニでの現金払い
- 口座振替
- クレジットカード決済
- ペイジー(オンラインバンキングによる支払い)
共有持分の場合も、原則として各共有者が持分に応じて固定資産税を負担することになります。ただし、納税通知書は代表者(代表共有者)に一括で送付される場合が多いため、実務上の調整が必要になるケースも少なくありません。
関連記事:共有名義の「固定資産税」は誰が払うべき? 滞納した場合や支払いたくない場合はどうなる?
都市計画税
都市計画税は、所有する不動産が「都市計画法による市街化区域」に位置している場合に課される地方税です。この税金は、都市インフラ整備(道路、公園、下水道など)の財源を確保するために徴収されています。
(参考:総務省「都市計画税」)
税額の算定方法は次のとおりです。
- 税額 = 固定資産税評価額 × 0.3%(上限税率)
実際の適用税率は市町村ごとに設定されますが、0.3%を超えることは法律上認められていません。都市計画税も、固定資産税と同様に、持分割合に応じた負担が基本となります。
所有時に使える可能性のある控除・軽減制度
新築住宅に対する固定資産税の軽減措置
新築住宅を取得した場合、条件を満たすことで、固定資産税が一定期間軽減される特例が適用されます。共有持分で取得した場合も、持分割合に応じて適用可能です。
| 区分 | 内容 |
| 軽減内容 | 固定資産税の課税標準額を2分の1に軽減 |
| 適用期間 | 一戸建て住宅:新築後3年間 耐火・準耐火構造(マンション等):新築後5年間 |
| 主な適用条件 | – 自己の居住用であること(投資目的不可) – 延床面積が50㎡以上280㎡以下(共同住宅の場合は40㎡以上) – 指定の期間までに新築された住宅 – 建築確認済証を取得していること |
(参考:国土交通省「新築住宅に係る税額の減額措置」)
なお、この特例は、「新築=自動適用」ではありません。 登記後に市区町村へ軽減申告書を提出しないと、軽減措置が適用されない自治体もあります。
また、共有持分の場合、他の共有者が要件を満たしていないとトラブルになる可能性があるため、事前に相談・調整をしておくことが重要です。自己居住用でなかったり、投資用として使用したりすると、軽減対象から外れてしまうので注意しましょう。
認定長期優良住宅に対する軽減措置
標準特例よりもさらに条件が厳しいですが、「認定長期優良住宅」として認定を受けた住宅については、固定資産税の軽減期間が延長されます。
| 区分 | 内容 |
| 軽減内容 | 固定資産税の課税標準額を2分の1に軽減(標準特例と同じ) |
| 適用期間 | 一戸建て住宅:新築後5年間 耐火・準耐火構造(マンション等):新築後7年間 |
| 主な適用条件 | – 長期優良住宅として認定を受けていること – 自己の居住用であること – 建築基準法を上回る耐震性・省エネ性などを満たしていること |
(参考:国土交通省「認定長期優良住宅に関する特例措置」)
認定長期優良住宅の取得は、確かに税制メリットが大きいですが、取得までのハードルが高めです。具体的には、建築費が割高になったり、追加の書類提出や手続き負担が発生する場合もあります。
また、共有持分で適用する場合は、全員が自己居住用として使用する必要があるため、誰かが投資用にすると軽減対象から外れるリスクもあります。
共有持分を「取得」したときに発生する税金
共有持分を取得するとは、売買、贈与、相続などによって不動産の持分権を新たに取得することを指します。単に権利を得るだけでなく、登記手続きや各種税金の支払いも必要となるため、事前に発生する負担を把握しておくことが重要です。
共有持分を取得した場合に発生する主な税金は、以下のとおりです。
- 不動産取得税
- 贈与税
- 相続税
- 登録免許税
次項より、それぞれ個別に解説していきます。
所有時に発生する税金一覧
不動産取得税
購入や贈与によって共有持分を取得した場合、都道府県から不動産取得税が課されます。ただし、相続による取得は対象外です。
(参考:国税庁「土地や建物を売ったとき」)
取得後半年から1年半程度で、各都道府県から納税通知が届きます。その後、金融機関にて納税するという流れを採ります。
税額は以下の計算式で算出されます。
- 土地・建物の税額 = 固定資産税評価額 × 4%(標準税率)
ただし、2024年3月31日までの特例措置で、通常の4%が3%になります。さらに宅地評価の土地は、特例により固定資産税評価額を半額にして計算します。なお、住宅については、新築ならば1,200万円の控除を受けることが可能です。
関連記事:共有持分を取得した場合にかかる「取得税」とは?節税対策もセットで解説
贈与税
贈与税は、贈与により財産を無料・低額譲受などで得たときにかかる税金です。不動産の場合、土地や建物を贈与されたり、住宅などの購入資金を援助されたりしたタイミングで対象となります。
(参考:国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」)
贈与税では、毎年1月1日~12月31日まで(1暦年中)合計金額から、基礎控除額である110万円を差し引いた残額に贈与税を課す方式がとられています。これを暦年課税といいます。
平成27年以降の贈与税の税率は、「一般贈与財産」「特例贈与財産」の2つに分けられました。
特例贈与財産は、贈与によって財産を得た人(18歳以上で、贈与を受けた年の1月1日における状況)が、直系尊属(父母や祖父母など)から取得した財産の贈与税を計算する際に使用するための区分です。
各区分の贈与税の税率は、以下のとおりです。
<一般贈与財産用(一般税率)>
| 課税価格範囲(基礎控除後) | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | – |
| 200万円超〜300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 300万円超〜400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 400万円超〜6,000万円以下 | 30% | 65万円 |
| 6,000万円超〜1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超〜1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 1,500万円超〜3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
<特例贈与財産用(特例税率)>
| 課税価格範囲(基礎控除後) | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | – |
| 200万円超〜400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円超〜600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 600万円超〜1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,000万円超〜1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 1,500万円超〜3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 3,000万円超〜4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
なお、2,500万円までの贈与は、贈与者が死亡したときに相続税と合わせて課税・清算する「相続時精算課税」も存在します。
将来の相続が確定的な間柄での贈与に限られますし、他にも一定の条件が存在するものの、あわせて把握しておきましょう。
関連記事:親子共有名義の不動産は生前贈与するべき?注意点について徹底解説!
関連記事:共有持分を贈与する際の「贈与税の計算方法」をわかりやすく解説!
相続税
相続税は、相続人が相続などで取得する財産に対して課税されます。
相続税は、相続した全財産(正味の遺産)から基礎控除額を引いた後の金額を法定相続分で「按分」し、その金額に税率を適用して計算した金額の合計額(相続税の総額)を相続する財産の割合に応じて、さらに按分して計算する税金です。
相続税の計算式と税率は以下のとおりです。
【相続の基礎控除額】
- 3,000万円 + 600万円× 法定相続人の数
【法定相続分に応じた税率】
| 法定相続に応じた金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | 0円 |
| 1,000万円〜3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円〜5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円〜1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円〜2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円〜3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円〜6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
(参考:国税庁「相続税」)
相続税は、相続が開始した日の翌日から10ヶ月以内に申告・納税しなければなりません。期限を過ぎると特例が適用できなくなる他追加の税金が発生しかねないため、留意しましょう。
登録免許税
登録免許税は、不動産の登記に関連する税金で、法務局に納税する形で支払います。その金額は、不動産の「固定資産税評価額 × 登録免許税率」によって算出されます。
共有持分移転登記の場合、所有割合が計算に含まれるため注意が必要。登録免許税率は下記の計算式で算出します。
<建物の登記>
| 内容 | 税率 |
|---|---|
| 所有権の保存 | 0.4% |
| 売買または競売による所有権の移転 | 2% |
| 相続または法人の合併による所有権の移転 | 0.4% |
| その他の所有権の移転(贈与・交換・収用等) | 2% |
(参考:国税庁「登録免許税の税額表」)
関連記事:共有持分移転登記費用はいくらかかる?登記の際の注意点についても解説
取得時に使える可能性のある控除・軽減制度
新築住宅に対する不動産取得税の軽減措置
自己居住用の新築住宅を取得した場合、不動産取得税が軽減される制度があります。共有持分で取得した場合も、持分割合に応じて適用されます。
| 区分 | 内容 |
| 軽減内容 | – 建物:固定資産税評価額から最大1,200万円控除 – 土地:評価額の2分の1を基礎に課税 |
| 税率 | 通常4% → 特例期間中(令和6年3月31日まで)は3%に引き下げ |
| 主な適用条件 | – 自己居住用であること(投資用不可) – 延床面積が50㎡以上280㎡以下(共同住宅の場合は40㎡以上) – 建築確認済証を取得していること |
(参考:国土交通省「不動産取得税に係る特例措置」)
新築住宅でも、別荘や投資用として購入した場合は適用外となります。また、中古住宅の場合はこの特例が使えないケースも多いため、「築年数」「未使用かどうか」などを購入前に必ず確認しておきましょう。
認定長期優良住宅に対する不動産取得税・登録免許税の軽減
前述した認定長期優良住宅に対する各種税制優遇措置のうち、ここでは「登録免許税の軽減」に関する内容を整理します。登記にかかる負担を大きく抑えられるため、共有持分の取得でも重要なポイントとなります。
認定長期優良住宅を取得した場合、不動産取得税・登録免許税の両方で大きな軽減措置が受けられます。
| 区分 | 内容 |
| 不動産取得税の軽減 | 固定資産税評価額から最大1,300万円控除 |
| 登録免許税の軽減 | – 所有権保存登記:0.4% → 0.1%に軽減 – 所有権移転登記:2% → 0.2%に軽減 |
| 主な適用条件 | – 取得時点で長期優良住宅の認定を受けていること – 自己居住用に供すること – 登記時に認定通知書など必要書類を提出できること |
(参考:国土交通省「認定長期優良住宅に関する特例措置」)
この特例は手続きが非常に煩雑です。特に、認定書類の取得には設計段階からの申請が必要で、完成後に取得することは基本的にできません。
購入物件が「認定済み」であることを必ず確認し、かつ認定内容に変更がないかも注意しておきましょう。
住宅ローン控除(※条件を満たす場合)
住宅ローンを利用して共有持分を取得した場合、一定の条件を満たせば「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」を利用できます。
| 区分 | 内容 |
| 控除額 | 年末のローン残高の0.7%を所得税から控除(最大13年間) |
| 主な適用条件 | – 取得した住宅に自ら居住していること – 住宅の床面積が40㎡以上 – 住宅ローンの返済期間が10年以上 – 取得価格が一定額以下であること(新築4,500万円以下など) |
(参考:国税庁「認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」)
共有持分でも、各人がそれぞれローン契約を結び、各自で申告する必要があります。また、親子間共有の場合など、ローン契約や登記割合にズレがあると控除が受けられないケースもあるため、契約時から慎重に進めましょう。
相続時精算課税制度(※贈与時)
共有持分を贈与で取得する場合、一定の条件下で相続時精算課税制度を利用可能です。
| 区分 | 内容 |
| 軽減内容 | – 2,500万円までの贈与について贈与税が非課税 – 贈与者死亡時に相続税と合算して精算 |
| 主な適用条件 | – 贈与者が60歳以上の父母または祖父母 – 受贈者が18歳以上の子または孫 – 特別な届け出(「相続時精算課税選択届出書」)が必要 |
(参考:国税庁「相続時精算課税の選択」)
この制度を一度選択すると、以後すべての贈与に適用されるため、簡単には取り消しできません。相続税を考慮したうえで、慎重に判断する必要があります。
配偶者控除(※贈与時)
配偶者間で共有持分を贈与する場合、条件を満たせば贈与税の配偶者控除が利用できます。
| 区分 | 内容 |
| 軽減内容 | 最大2,000万円までの贈与について贈与税が非課税 |
| 主な適用条件 | – 婚姻期間が20年以上 – 贈与された財産が居住用不動産またはその購入資金 – 贈与後も引き続き居住すること |
(参考:国税庁「配偶者控除」)
適用は一生に一度だけの特例です。また、一般の基礎控除110万円とは併用可能なため、合計2,110万円まで贈与しても贈与税がかからない仕組みとなっています。
共有持分を「売却」すると発生する税金
共有持分を売却するとは、自分が所有している不動産の持分権を第三者または共有者に譲渡することを指します。
売却によって現金化できる一方で、一定の利益が生じた場合には、所得税や住民税といった税金が課されることになります。また、売買契約書に対しても別途印紙税が発生するため、売却益だけでなく税負担まで見越して計画を立てることが大切です。
共有持分を売却した場合に発生する代表的な税金は、以下の3種類です。
- 譲渡所得税
- 住民税
- 印紙税
それぞれの税金がどのような仕組みで発生し、どのタイミングで支払う必要があるのか、次項から個別に詳しく解説していきます。
売却時に発生する税金一覧
譲渡所得税
不動産を売却した際の利益は譲渡所得として所得税と住民税の対象となり、これがいわゆる譲渡所得税です。この譲渡所得は他の所得とは別に計算され、分離課税となります。
(参考:国税庁「土地や建物を売ったとき」)
不動産を売却した際の売却価格から取得費や諸経費を引いた額が、不動産を取得した際の価格を超えた場合に課税される方式です。
譲渡所得税の税率は不動産の所有期間により変わり、5年以下(短期譲渡所得)と5年超(長期譲渡所得)の2つに分けられます。この所有期間は売却した年の1月1日を基準に計算されます。
| 所得税 | 住民税 | 復興特別所得税 | 合計 | |
| 短期譲渡所得(5年以内) | 30% | 9% | 0.63% | 39.63% |
| 長期譲渡所得(5年超) | 15% | 5% | 0.32% | 20.32% |
(参考:国税庁「短期譲渡所得の税額の計算」「長期譲渡所得の税額の計算」)
関連記事:共有持分の譲渡でかかる「税金」はどれ?納税額の計算方法とは
関連記事:共有不動産の売却でも「確定申告」は必要?やり方と注意点について紹介
印紙税
共有持分を売却する際には、売買契約書に対して課税される税金である「印紙税」を支払う必要もあります。印紙税は、売買契約書に収入印紙を貼り付ける形で納税する仕組みで、印紙代は取引金額によって以下のように変動します。
| 契約金額 | 印紙代 |
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1〜10万円 | 200円 |
| 10〜50万円 | 400円 |
| 50〜100万円 | 1,000円 |
| 100〜500万円 | 2,000円 |
| 500〜1,000万円 | 1万円 |
| 1,000〜5,000万円 | 2万円 |
| 5,000万〜1億円 | 6万円 |
| 1億〜5億円 | 10万円 |
| 5億〜10億円 | 20万円 |
| 10億〜50億円 | 40万円 |
| 50億〜 | 60万円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 |
(参考:国税庁「印紙税」)
なお、共有持分を売却するという特性上、契約金額が1,000万円を超えるケースはそこまでないでしょう。そのため「印紙税は大してかからない」と理解しても問題ありません。
売却に使える可能性のある控除・軽減制度
居住用財産を売却した場合の3,000万円特別控除
自己の居住用に使用していた不動産(共有持分を含む)を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。
| 区分 | 内容 |
| 控除額 | 譲渡所得から最大3,000万円を控除 |
| 適用条件 | – 自己の居住用であったこと – 売却した年の1月1日時点で空き家でないこと – 原則、譲渡前年及び前々年に同特例を適用していないこと |
(参考:国税庁「マイホームを売ったときの特例」)
持分売却であっても、自ら居住していた実態があればこの控除を適用可能です。ただし、相手方が家族だった場合(身内間売買)など、実態が問われるケースでは適用を否認される可能性もあるため注意が必要です。
居住用財産の譲渡に係る軽減税率特例
所有期間が10年以上の居住用財産を売却した場合、譲渡所得税率がさらに軽減される特例です。
| 区分 | 内容 |
| 軽減内容 | – 6,000万円以下の部分:所得税10%+住民税4% – 6,000万円超の部分:所得税15%+住民税5% |
| 適用条件 | – 居住用財産であること – 所有期間が10年以上あること – 売却年の前年・前々年に特例を適用していないこと |
(参考:国税庁「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」)
通常、長期譲渡所得は所得税15%+住民税5%ですが、この特例を使うとさらに税率が下がります。3,000万円特別控除と併用できるため、譲渡益が大きい場合でも節税効果が高まります。
相続した空き家を売却した場合の特例(空き家特例)
相続によって取得した空き家を一定の条件下で売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。
| 区分 | 内容 |
| 控除額 | 譲渡所得から最大3,000万円を控除 |
| う適用条件 | – 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること(耐震改修済みを除く) – 被相続人が居住していたこと – 相続から売却までに第三者に貸し付けていないこと – 売却価格が1億円以下であること |
(参考:国税庁「マイホームを売ったときの特例」)
この特例は、共有持分のみ売却する場合には原則適用できません。不動産全体(共有物全体)を売却する必要があるため、共有者全員での売却を前提に検討する必要があります。
また、事前に耐震診断や改修工事が求められる場合もあるため念頭に置いておきましょう。
共有持分の税金負担に悩んだら、「ワケガイ」でスムーズな解決を

当社(株式会社ネクスウィル)は、共有持分をはじめとする訳あり不動産に特化した買取サービス「ワケガイ」を提供しています。
共有持分は、所有しているだけでも固定資産税などの支払い義務が生じ、売却や取得のタイミングではさらに複雑な税金が関わってきます。控除制度も存在するものの、適用には厳しい条件が多く、思ったような負担軽減ができないケースも少なくありません。
ワケガイでは、そうした共有持分ならではの悩みを理解したうえで、現状のまま買取に応じることが可能です。面倒な手続きやトラブルを回避し、スムーズな資金化を実現します。
まずは、お気軽に無料査定をご活用ください。
まとめ
共有持分にかかる税金は、所有・取得・売却といった局面ごとに大きく異なります。それぞれのフェーズで適切な税金計算を行い、利用できる控除・軽減制度を正しく押さえておくことが、余計な負担を避けるためには不可欠です。
特に、控除制度には細かな適用条件があるため、「使えるはず」と思い込まず、事前に要件を丁寧に確認してから動く必要があります。
また、共有持分特有のリスクとして、他の共有者との利害調整が複雑になるケースもあるため、必要に応じて専門家への相談も視野に入れることが大切です。
整理した知識をベースに、納税義務を見落とさず、より賢く共有持分と向き合っていきましょう。